採用活動に適性検査を活用しよう|種類・選ぶ際のポイントも解説

Check!
- 適性検査は、応募者の資質見極めだけでなく、より多くの求職者を集める目的でも使える
- 新卒採用と中途採用は目的が違うため、適性検査において注目すべきポイントも異なる
- 適性検査を選ぶ際は、受験方法・所要時間・結果が出るまでの時間・費用などを確認する
採用活動においては、適性検査を実施することで、履歴書や面接では知り得ない応募者の潜在的な能力や性格を把握することができます。また適性検査は、より多くの求職者を集めるためのツールとしても有効です。この記事では、適性検査の種類・目的・選び方などを解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
この記事に掲載されているサービス
-
-
-
TG-WEB
- 資料ダウンロード
-
成果を生み出す人材を見極めるなら適性検査サービスがおすすめ
TG-WEBは、業界初のオンラインAI監視型Webテストにより、応募者の利便性向上と公正・公平な採用試験を実現できる適性検査サービスです。一般的な適性検査に加え、豊富に用意されたプランから自社独自のカスタマイズで検査を行えます。
例えば、コンピテンシー適性検査 A8では、「コンピテンシー=成果を創出するための能力」という視点で人材を評価し、自社で長期的に活躍するハイパフォーマー(高業績者)の創出にもつなげられます。
また、実際に成果を生み出す人材なのかを見極めることで、質の高い採用活動や効果的な傾向分析などに活用できます。金融業界レベルのセキュリティ水準を確保し、長期的なデータの蓄積・分析で自社にマッチした人材を確保したいなら、TG-WEBの導入がおすすめです。
適性検査を採用活動に役立てよう

適性検査とは、採用活動を行う際に応募者がどんな職場が適しているかを知るために、総合的に評価するためのテストです。このテストを実施することで、履歴書や面接だけでは知り得ない応募者の潜在的な能力や性格を把握できます。
また、適性検査は、より多くの求職者を集めるためのツールとしても有効です。この記事では、適性検査の種類・目的・選び方などを解説します。

適性検査とは?メリット・デメリットやSPIとの違いについても解説
適性検査とは、個人の能力・性格・特性を定量的かつ客観的に測定する試験のことです。人材採用後のミスマッチの予防や、適切な人員配置を行う目的で活用されています。この記事では、企業が適性検査を利用するメリット・デメリット、実施方法などを解説します。
適性検査の種類
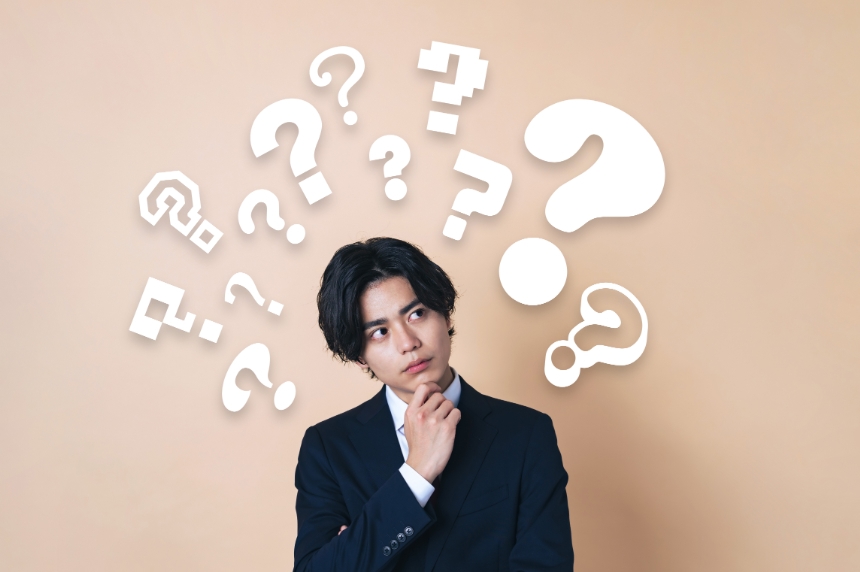
適性検査は一般的に、性格検査と能力検査の2種類に大別されます。以下では、それぞれの検査についての概要、何が測定できるかを詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
性格検査
性格検査とは、応募者の思考や言動に関する質問に回答してもらい、その結果を統計的に処理することで、性格的な特徴を把握するための検査です。具体的に性格検査では、ストレス耐性や協調性、リーダーシップ、責任感、社交性などが測定されます。
例えば、ストレス耐性を測る質問では、「プレッシャーがかかる状況でも冷静に対処できるか」といったことや、協調性については「チームで働くことを好むか」などの質問があります。
これらの質問に対する応募者の回答を分析することで、応募者がどのような性格であり、どのような職場環境や仕事に適しているかを見極めることができます。性格検査を行うことで、適切なポジションに配置可能になります。
能力検査
能力検査とは、応募者の基礎的な学力や知識を評価するためのテストです。具体的には、問題を正しく理解し、適切な方法で解決する力を測ります。例えば、論理的思考力や数的処理能力、言語理解力などが評価されます。
論理的思考力のテストでは、論理パズルや推理問題が出題され、応募者が複雑な問題をどのように解決するかを見ます。これらの検査結果を分析することで、企業は応募者が仕事を効率的に進めるために必要なスキルを持っているかどうかを判断します。
適性検査の目的

適性検査を実施することには、応募者の資質を見極めたり、求職者を集めたりなどさまざまな目的があります。以下では、その目的について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
適性検査の目的
応募者の資質を見極める
適性検査の目的は、採用活動において応募者の資質を客観的に評価することにあります。履歴書や面接ではわかりにくい応募者の潜在的な能力や性格を把握し、どのような仕事や職場環境に適しているかを判断するために適性検査が利用されます。
この検査を通じて、企業は応募者が持つ特定のスキルや能力を客観的に評価し、それに基づいて最適な人材選考を行うことができます。
例えば、性格検査では応募者のストレス耐性や協調性、リーダーシップ能力を評価し、その人がチームで働く能力や責任感をどれだけ持っているかを判断します。
求職者を集める
適性検査は、求職者を客観的に評価するだけでなく、求職者自身にとっても重要なメリットがあります。結果をフィードバックすることで、求職者は自身の能力や特性を客観的に知ることができ、自己分析やキャリアプランニングに役立てることができます。
応募者は自分に合った職種や業務環境をより明確に把握し、自己理解を深めることができます。適性検査を実施し、その結果を丁寧にフィードバックすることで、企業は求職者に対して誠実で透明な姿勢を示し、多くの優れた人材を引きつけることが可能です。
接触の機会を設ける
適性検査は、求職者の能力や適性を客観的に評価するだけでなく、求職者と企業との接触の機会を設ける目的もあります。特にフィードバック時の面談は、企業が自社をアピールし、求職者の志望度を高める場として活用されます。
このフィードバックは、応募者が自身の強みや改善点を把握するサポートとなるだけでなく、同時に企業の仕事環境や文化、将来について理解する良い機会でもあります。
企業は面談を通じて自社の魅力や成長の機会を伝え、応募者にとって魅力的な職場であることを示すことができます。
新卒採用向け・中途採用向け適性検査の違い
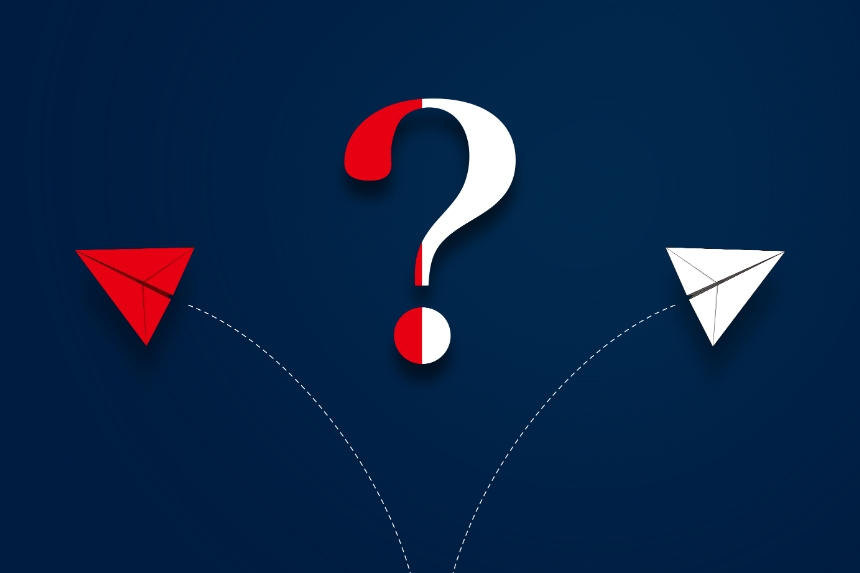
新卒採用と中途採用における適性検査では、注目すべき検査項目に違いがあります。以下では、それぞれの適性検査の違いについて、詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
新卒採用の場合
新卒採用における適性検査の主な目的は、応募者の基本的な能力や適性を客観的に評価し、面接に進む候補者の優先順位を付けることです。新卒者は職務経験がないため、履歴書や学歴だけでは判断しづらい部分があります。
そこで、適性検査を用いることで、面接だけではわからない学生の潜在的な能力や性格を把握し、将来の成長性や適応力を予測できます。
適性検査で注目すべきポイントは、主に基本的な学力や論理的思考力、コミュニケーション能力、そして性格や適応力などです。これらの要素は、入社後の業務において必要となるスキルや素質を見極めるために重要です。
中途採用の場合
中途採用の目的には、既に一定の経験やスキルを持つ候補者が、企業の現場でどれだけ成果を上げられるかを評価することが挙げられます。新卒採用とは異なり、中途採用では応募者の職務経験や実績が重要視されます。
そのため、履歴書や職務経歴書、面接だけでなく、適性検査を通じてさらに詳しく候補者の適性を見極めることが求められます。中途採用における適性検査で注目すべきポイントは、まず応募者のパーソナリティや性格です。
たとえば、協調性が高いか、リーダーシップを発揮できるか、ストレス耐性があるかなどが評価されます。
適性検査を活用することで、中途採用の精度を高め、企業のニーズに最も適した人材を見つけることができます。結果として、即戦力として活躍できるだけでなく、企業の成長に寄与する優秀な人材を確保することが可能となります。
適性検査実施のタイミング

適性検査は、採用のさまざまな段階で実施されることがあります。具体的には、書類選考を通過した後や一次面接の前後、そして最終面接前(内定前)のタイミングで行われることが一般的です。
以下では、それぞれのタイミングで適正検査を行うメリット・デメリットなどを解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
適性検査実施のタイミング
書類選考時
適性検査を書類選考時に実施することには、いくつかのメリットとデメリットがあります。まず、メリットとして、書類選考で明確に自社の求める条件に合わない候補者を早い段階で特定できる点が挙げられます。
適性検査によって、応募者の基本的な能力や適性が客観的に評価されるため、自社の業務や文化に合致しない可能性が高い候補者を事前に排除できます。
一方でデメリットとしては、適性検査の受検人数が多くなることで、実施費用が増大することがあります。大量の応募者に対して適性検査を行う場合、テストの準備や実施にかかるコストが増えるため、企業側にとって経済的な負担が大きくなる可能性があります。
一次面接の前後
一次面接の後に適性検査を面接の日程と同じ日に行うことで、日程や会場の調整の手間を省くことができます。応募者にとっても一度に面接と適性検査を受けることで、時間や交通費の節約になる利点があります。
しかし、書類選考後に行う場合と比べて、適性検査の足切り効果は低くなることがあります。
一次面接での対面での評価に加えて、適性検査の結果を待つことで、より深い洞察が得られるという点でメリットがある反面、採用プロセス全体の効率性に影響を与える可能性も考慮しなければなりません。
最終面接時(内定前)
最終面接時(内定前)に適性検査を実施することで、応募者の最終的な適性や能力を評価するための重要な材料となります。これにより、内定者を選定する際に客観的な判断が可能となり、組織への適合度をより確実に評価できます。
適性検査は、履歴書や面接だけでは把握しきれない潜在的な能力や性格を明らかにする手段として、非常に有効です。しかし、最終面接という緊張感のある場面で適性検査を受けることで、不安感が増し、本来の実力を発揮できない場合も考えられます。
また、適性検査の結果に過度に依存することで、面接での印象や他の評価基準が軽視されるリスクもあります。
適性検査を選ぶ際のポイント

適性検査を選定する際には、企業や求職者のニーズに合った適切な検査方法や内容を選ぶことが重要です。それには、検査の信頼性や妥当性、適用範囲、費用対効果など、さまざまな観点から検討する必要があります。
適性検査を選ぶ際に重要なポイントを以下で詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
適性検査を選ぶ際のポイント
受験方法
適性検査を選ぶ際に重要なポイントの一つは、受験方法の選択です。適性検査は、主にWeb試験や紙試験、テストセンター、インハウスの4つの方法で受けることができます。
これらの受験方法は、それぞれの企業の方針や応募者の利便性に合わせて選択すべきです。以下の表はそれぞれの実施方法のメリット・デメリットです。
| 実施方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| Web試験 | ・自宅や任意の場所から受験可能 ・受験日時の柔軟性がある | ・インターネット接続が必要 ・受験時のネットワークやシステムの問題が影響する可能性がある |
| 紙試験 | ・PC操作に慣れていなくても受験可能 | ・答案用紙の送付や受領に時間がかかる場合がある ・試験会場への移動が必要 |
| テストセンター | ・検査環境が整備されている | ・会場までの移動時間や交通費がかかる場合がある |
| インハウス | ・面接との連携がスムーズに行えることが多い ・会社の雰囲気や環境を直接感じることができる | ・企業の都合により受験日時が限られることがある |
自宅受験型テストの広まり
近年、自宅で受験できるタイプの適性検査が増えています。これは、インターネット環境さえあれば、場所を選ばずに受験できる形式です。
従来のテストセンターでの受験に比べて、会場に出向く時間が不要であり、自宅や学校など受験者が慣れ親しんだ環境で受験することができます。遠方に住む受験者や、移動が難しい人にとっても検査を受けることが容易です。
利用目的に合っているか
利用目的によって適性検査を選ぶ際、考慮すべきポイントは異なります。そのため、利用目的に合わせて適正検査を選ぶ必要があります。以下では、その利用目的に合わせて、適正検査を選ぶときにチェックすべきポイントについて解説します。
応募者の素質を見極めたい場合
応募者の素質を見極めるために適性検査を活用する際には、どのような能力や特性を測定し、それを数値化できるかを検討することが重要です。例えば、数理能力やコミュニケーションスキル、ストレス耐性などがその一例です。
これらのテスト結果は数値化され、応募者の能力を客観的に比較する基準となります。適性検査を導入する際には、自社の業務内容や求める人物像に合わせて、どのような能力を重視するのかを明確にし、それに応じたテスト項目を選定することが大切です。
求職者を集めたい場合
求職者を集めるために適性検査を活用する際に重要なポイントは、応募者がフィードバック結果をどれだけ見やすく理解できるか、求職者が知りたい情報をどれだけ提供できるかです。
また、求職者の関心度や着目度を高めるために、適性検査の受検結果を集客促進のコンテンツとして活用する方法もあります。
例えば、フィードバックシートには、求職者の強みや改善点を具体的に記載し、それに対するアドバイスも加えると良いでしょう。また、求職者が結果をもとに自己分析を行い、自分のキャリアについて考える時間を持てるようにすることも重要です。
このような工夫をすることで、適性検査は単なる評価ツールではなく、求職者にとって有益なツールとなり、結果的に多くの応募者を集めることができるでしょう。
接触の機会を設けたい場合
接触の機会を設けるために適性検査を活用する際、フィードバック面談の実施がしやすいかどうかをチェックすべきです。適性検査のフィードバックを活用し、フィードバック面談やキャリア面談を通じて受験者との深い対話を促進することが効果的です。
さらに、適性検査の結果が面談や会話を盛り上げる要素となるかどうかも重要です。たとえば、特定の能力や性格特性に関する結果が、受検者と面接官の共通の話題や関心事と結びつけば、会話が深まりやすくなります。
受験にかかる所要時間
適性検査の受験にかかる所要時間は、受験者にとっても管理側にとっても重要な要素です。一般的に、適性検査の所要時間はテストの内容や形式によって大きく異なり、短いもので20分程度、長いものでは2時間にも及ぶことがあります。
そのため、適性検査を選ぶ際には、その所要時間も考慮する必要があります。受験者が無理なく受験できる時間内で、必要な情報を正確に測定できるテストを選ぶことが理想的です。
結果が出るまでの時間
適性検査の結果が出るまでの時間は、利用するサービスによって大きく異なるため、事前に確認しておくことが重要です。一般的に結果が早く出るサービスでは、当日から翌日には結果を確認できることが多いです。
一方で、結果が出るまでに時間がかかるサービスもあります。遅くとも一週間以内には結果が出ることが多いですが、それ以上かかる場合もあります。
適性検査の結果が出るまでの時間は、採用活動のスピードと応募者の満足度に大きく影響します。そのため、事前にサービスの詳細を確認し、迅速な結果を提供できるものを選ぶことが望ましいです。
必要な費用
適性検査を導入する際に考慮すべきポイントは、必要な費用です。サービスによって費用にはかなり幅があり、企業の予算に見合うかどうかを事前に確認することが重要です。
適性検査を導入する際に、初期費用・システム利用料が発生する場合がありますが、最近では無料のツールも提供されているため、予算に応じて選ぶことが可能です。受検料は、受験する人数や科目数によって異なります。
受検者が大量にいる場合、人数に応じた割引が適用されることもあります。以上のように、適性検査を選ぶ際には、初期費用やシステム利用料、受検料といったコスト面を総合的に考慮することが重要です。
採用時に適性検査を活用する際の注意点

適性検査を効果的に活用するためには、いくつかの重要な注意点があります。これらの注意点に考慮できないと、適性検査の結果を正確に解釈できず、採用活動が期待通りの成果を上げられない可能性があります。
ここでは、適性検査を採用時に活用する際の具体的な注意点について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
採用時に適性検査を活用する際の注意点
不正防止対策を行う
採用時に適性検査を活用する際には、不正防止対策をしっかりと行うことが重要です。特に自宅で受験するWeb形式では、身代わり受検などの不正が起こりやすいリスクがあります。
このような不正行為を防ぐためには、対策を講じることが必要です。例えば、オンライン検査で監督者を配置することが有効です。監督者がいることで、受検者の行動をリアルタイムで監視し、不正行為を防止できます。
また、受検前には身分証を確認しましょう。これにより、身代わり受検のリスクを減らすことができます。このように、不正防止対策をしっかりと行うことが重要です。
選考通過のボーダーラインを決めておく
採用時に適性検査を活用する際には、選考通過のボーダーラインを事前に決めておくことが重要です。具体的には、どのくらいの学力が最低限必要なのか、どのような性格傾向を持つ人が適しているのかといった基準を明確にしておく必要があります。
例えば、テストの総得点のうち60%以上を獲得した場合に次の選考に進む、といった具体的な数値を決めておくと良いでしょう。この基準を決める際には、既存の社員に同じ適性検査を受験してもらうことをおすすめします。
既存社員の結果を参考にすることで、実際にその企業で活躍している人の傾向を把握し、適切な基準を設定することができます。
適性検査の結果だけを当てにしない
採用時に適性検査を活用する際には、適性検査の結果だけを当てにするべきではありません。適性検査は、応募者の能力や性格を客観的に評価する有力なツールですが、それだけでは個人の多面的な特性や個性を完全に理解することはできません。
また、適性検査の結果だけに頼ると、個々の応募者の持つポテンシャルや成長の可能性を見落としてしまうこともあります。特に新卒採用の場合、実務経験がないため、適性検査だけで判断するのは難しいです。
面接やグループディスカッションなどを通じて、その人がどのような考え方を持ち、どのように問題に取り組むかを直接観察することが大切です。
採用活動以外での適性検査の活用方法

適性検査は採用活動以外でも、従業員の能力開発や異動時の判断材料など様々な場面で活用されています。以下では、その活用例と具体例について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
採用活動以外での適性検査の活用方法
従業員の能力開発に活用する
適性検査は、採用活動だけでなく従業員の能力開発にも有効に活用されます。従業員一人ひとりの適性や能力を評価し、それに基づいた個別の育成プランを立てることができます。
例えば、コミュニケーションスタイルやリーダーシップの特性を把握することで、各従業員がより効果的にチームでの役割を果たすための研修やフィードバックを提供できます。
異動時の判断材料として活用する
適性検査は、従業員の異動時において重要な判断材料として活用されます。たとえば、従業員の関係構築や交渉能力が高い場合、営業部門での活躍が期待されるかもしれません。
一方でリーダーシップの能力が優れている場合は、企画部門やプロジェクトリーダーとしてのポジションが適している可能性があります。
適性検査の結果を元にこれらの特性を的確に評価し、適材適所の配置を行うことで、従業員のモチベーションや成果の最大化を図ることができます。
マネージャー・リーダーの評価に活用する
適性検査を実施することで、候補者が将来のポジションで必要とされるスキルや特性を評価できます。たとえば、リーダーシップや意思決定能力、コミュニケーションスキルなどがその一例です。
これにより、昇進後に必要な適性を備えているかどうかを客観的に判断し、適材適所の人材配置をすることができます。また、部下のマネジメント能力を評価する際にも、適性検査の結果は有益です。
部下との関係構築やチームの指導力、問題解決能力などが含まれる場合、マネジャーやリーダーがこれらの面でどれだけ強みを持っているかを明確に把握することができます。
独自の高精度な検査が行えるおすすめの適性検査サービス
まとめ

適性検査は採用活動において、履歴書や面接だけでは把握しづらい応募者の潜在的な能力や性格を評価する重要なツールです。新卒採用と中途採用では、適性検査の目的や注目すべきポイントが異なります。
新卒採用では、未経験者に対する基本的な能力や適性を見極めることが重視されますが、中途採用では実務経験や専門知識に加えて、組織文化への適合性やリーダーシップ能力などが評価対象となります。
適性検査を選ぶ際には、受験方法(Webテスト、紙試験など)や所要時間(テストの長さ)、結果が出るまでの時間、費用(初期費用、利用料、受検料など)などを確認することが重要です。
企業のニーズや求職者の特性に合わせて最適な適性検査を選定し、効果的に活用しましょう。


