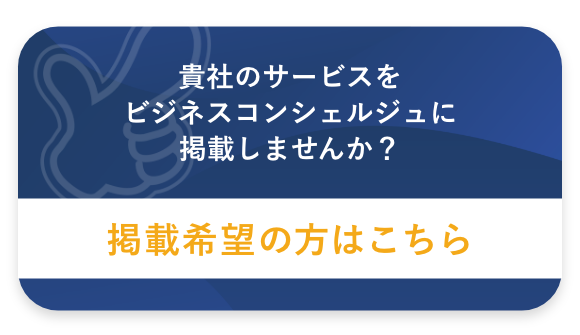勤怠管理の法律上のルールとは?違反を防ぐ注意点や管理方法も解説

Check!
- 法改正により、労働者の雇用に関する多くの法律は改正される方向へ向かっている
- 企業側は労働時間・有休取得率・残業時間などを正しく把握することが重要
- 法改正に正しく対応するには勤怠管理システムの導入がおすすめである
企業には勤怠管理を行う義務があり、詳しいルールは法律で定められているため、ルールを知ったうえで管理することが大切です。この記事では、勤怠管理の法的な意義や注意すべき法律のポイント、労働基準法の改正についての詳細や導入における注意点などを詳しく解説します。
おすすめ記事
勤怠管理の法的な意義とは

勤怠管理は、労働基準法で定められた企業が取り組むべき義務です。また、平成13年4月(基発第339号)の通告では、企業は従業員の勤務日単位での始業と終業の時間を把握し、これを正しく記録しなければならないとされています。
企業は、従業員の労働時間を正確に管理する義務がありますが、労働時間の把握だけでなく、そのほかにも守るべき規定が定められています。また、定められた期間の間、勤怠状況の記録保管も必要です。
労働基準法は、事業者や労働者が厳守しなければならない法律で、時間外労働・休日労働・深夜労働に関する規定も決められています。企業側は出勤日・始業・終業の時間だけでなく、労働時間を一日・週・月・年ごとの単位で正しく把握し、適切な管理が要求されます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
労働者を守るため
労働基準法をはじめとする労働に関しての法律には、労働者を守るといった大きな役割があります。しかし、長時間労働の常態化・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金格差・有給休暇取得率の低さなど、労働環境の悪化に直面しています。
さらに、育児や介護との両立などの家庭事情や、仕事と生活の調和重視といった個人の考え方に応じられる労働環境を望む声も年ごとに高まっています。
働き方改革関連法には、これらの問題解決と、多様な働き方の必要性に応じられる社会の実現で、労働者の働きやすい環境整備と柔軟な働き方の受容による労働力確保の目的があります。
企業を守るため
労働基準法は、労働者だけでなく使用者側である企業を守る意味でも重要な法律です。労使間のトラブルには、解雇・退職・残業代の請求・長時間労働による過労死などに関するものや、中には、刑事責任が追及される場合もあります。
これらのトラブルへの対処や解決には、多額の経済的コストや人的コストが必要です。また、会社の評判や社会的な信用が低下するといったリスクもあります。労働基準法や関連法を守ることは、労使間のトラブルを防止するためにも重要です。
労働基準法の改正について

労働基準法は、昭和22年に制定された歴史ある法律です。太平洋戦争敗戦後、日本の産業復興に向けて制定された労働法の中でも基本となる法律でした。
スタートは、主な内容として、労働時間が週48時間・割増賃金は2割5分以上、そして労働時間が不規則になりがちな職種のための変形労働時間制(4週間を平均として週48時間以内の労働)が定められる程度のものでした。
しかし、労働基準法は情報化社会の発展に伴い、時代の要請に合わせてその様態を変えてきました。改正点の大部分は、労働時間と賃金に関する点です。ここでは、労働基準法の変遷について、主な改正点とその時代背景を紹介します。
【2019年から2023年に改正された労働基準法について】
最近の人手不足、長時間労働問題、さまざまな働き方(時短・フレックス・高齢者雇用・外国籍雇用・産後復帰など)へ対応するために、新しい働き方に対する労働基準法の改正を行いました。改正の主なポイントは以下の7点です。
- 残業時間の上限規制
- 年次有給休暇の取得義務化
- フレックスタイム制の改正
- 高度プロフェショナル制度
- 同一労働同一賃金による法改定
- 全労働者の育児・介護休暇取得が可能
- 中小事業主に対する時間外割増賃金率の適用
これらのうち、勤怠管理における対応を求められる5点について詳しく解説していきます。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
労働基準法の改正ポイント
残業時間の上限規制
法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超えて働く、時間外労働に上限が設定されました。残業時間を法律で規制するのは1947年以来のことで、大改革とまでいわれています。
改正前
法律上に残業時間の上限はなく、一定の残業時間を超過しても企業へは行政指導のみが行われていました。
法定労働時間・時間外労働の超過に関しても、労働基準監督署へ労働組合や従業員と締結する「36協定」を届け出れば規定を超えての労働が可能でした。
改正後
週40時間の時間外労働について変更はありませんが、36協定を締結していても上限が適用されます。
【原則】残業時間は月45時間、年360時間以内
※上記の制限を超える残業時間は年6回(年6ヶ月)に収めること
【例外適用時】残業時間は年720時間以内、2~6月の平均80時間以内、月100時間未満
参考:厚生労働省|月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます
年次有給休暇の取得義務化
2019年施行の改正労働基準法では、従業員の雇用日から6カ月間継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤した従業員は、原則として10日の年次有給休暇を取得できるようになっています。
雇用主は、年間10日以上の年次有給休暇を取得している従業員には、時季を指定して最低5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されました。
また、パートタイムなど所定勤務日数が少ない従業員は、年次有給休暇の日数が所定の労働日数に応じて与えられます。
改正前
雇用主は、従業員が雇用日から6ヶ月間継続勤務かつ全労働日のうち8割以上出勤した場合に、原則として10日の年次有給休暇を与えなければならない。
改正後
上記内容に加えて、取得時季を指定した上で年次有給休暇を付与した日から1年以内に最低5日間の有給休暇を取得させなければならない。
フレックスタイム制の改正
フレックスタイム制とは、従業員が始業・就業時間を自由に設定できる制度のことです。定められた「清算期間」のなかで労働時間の調整が可能なため、育児や介護と仕事の両立がより柔軟なものとなりました。
改正前
清算期間が1ヶ月
改正後
清算期間が1ヶ月~3ヶ月
高度プロフェショナル制度
新たに創設された高度プロフェショナル制度は、一定の年収要件を満たした特定高度専門業務・成果型労働制である特定の職種が対象です。労働基準法で定められた労働時間や休憩、割増賃金などの規定を適用しません。
しかし、長時間労働を防止する健康確保措置を講じるため、健康管理時間の把握や年間104日以上の休日確保措置がなされます。
中小事業主に対する時間外割増賃金率の適用
2023年4月には、中小企業を対象に割増賃金率が引き上げられました。従業員に月60時間を超える時間外労働を行わせた場合の割増賃金が変更となります。
改正前
中小企業のみ、月60時間を超える労働に対する割増賃金の割増率は25%
改正後
全企業、月60時間を超える労働に対する割増賃金の割増率は50%
勤怠管理で注意すべき法律のポイント

労働基準法においての勤怠管理は使用者側の義務です。最近の法改正により勤怠管理の正確さが要求されています。万一違反と認められた場合、罰則も課されるため注意が必要です。今回は勤怠管理で注意しておくべき労働基準法の重要なポイントを解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
勤怠管理で注意しておくべき労働基準法の重要なポイント
労働時間について
労働時間とは、労働者が使用者の管理下に置かれた時間を指し、拘束時間から休憩時間を除外した時間です。労働時間には、所定労働時間はもちろん、時間外労働・深夜労働・休日労働なども含まれており、出勤簿などで日ごとに細かく記録する必要があります。
また、タイムカードで残業代の計算をする際は、1日15分未満の残業時間は切り捨てといった行為は労働基準法の賃金全額払いの原則に反する行為です。1分単位での残業時間を記録し、月の残業時間を算出するのが決まりです。
ただし、1ヵ月の残業時間の集計結果については、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げて算出することが認められています。また、着替えの時間は労働時間として扱われます。
労働時間の把握方法について
労働基準法の第109条においては、労働者名簿・賃金台帳などの労働関係の重要書類の保管について定め、また、第108条では賃金台帳に記載しなければならない内容を定め、賃金の支払いごとに遅滞なく記入することが定められています。
労働関連法が改正される前も、厚生労働省の使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおいて、労働者の労働時間の把握は要求されていました。ただし、これらは適正な賃金の支払いを目的とする趣旨の方に重きを置いていました。
そのため、働き方改革関連法により、自由度の高い労働形態にも対応しつつ、長時間労働の改善といった労働者の健康と安全な職場環境の実現を目標として、労働安全衛生法第66条8の3において、労働者の労働時間把握が義務付けられています。
参考:労働時間の適正な把握のために – 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
年間休日総数について
労働基準法で規定されている年間休日の最低ラインは、1日8時間勤務の場合、年間105日と決められています。これは、法定休日(毎週か4週間の中で4日間以上の休日)と、法定労働時間(週40時間・1日最大8時間)をもとに算出されています。
1年間は52週で週に40時間働いた場合、年間の総労働時間は2,080時間です。それから1日当たりの労働時間8時間で割ると、労働日数としては260日になります。365日から労働日数260日を引くことで、年間休日の最低ラインが105日といったことが分かるでしょう。
法定休日に特定して設定すると52日となり、最低ラインには大幅に不足します。また、一般的な所定労働時間である1日8時間を前提とすると、週40時間である上限に達するため、完全週休2日制・長期休暇などの法定外休日を設定し年間休日を増やしていると言えます。
年次有給休暇の取得義務について
2019年4月の働き方改革法案の発足に伴い、年5日の年次有給休暇を与えることが義務付けられました。対象となる労働者は10日以上の有給休暇が付与された方となっており、正社員だけではなくパートやアルバイトも含まれます。
有給休暇は、出勤率や勤続年数によって違いがあるため、有給休暇についてもしっかりと把握しておきましょう。この法案に違反すると、違反者1人に対して最大30万円のペナルティが命じられます。
残業が60時間以上の場合について
使用者は、1カ月40時間を超える法定外残業に対して、割増賃金の支払いをしなければならないとの規定があります。さらに、1カ月60時間を超える残業を行った場合は、より高い割増率で残業代を支払う必要があります。
60時間には、週1日の法定休日に勤務した労働時間は含まれませんが、それ以外の休日労働については含めて計算しなければなりません。中小企業は2023年4月以降大企業と同じように、60時間超の残業に対して50%の割増賃金を支払う必要があります。
ただし、60時間を超える残業に対する割増賃金の代わりに、代替有給休暇を付与することが可能です。
参考:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省
法改正への対応は勤怠管理システムがおすすめ

2019年4月から労働基準法や労働安全衛生法などの大幅な改正が行われました。これにより、時間外労働の上限規制・有給休暇の取得義務化などが規定されています。違反した企業に対しては、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が与えられる場合があります。
これらの法律を厳守するためには、残業時間や有給休暇の管理を正確に行う必要があります。手書きのタイムカードといった管理方法は、人的コストがかかるうえに、正確さを欠くといったデメリットにつながります。
そのため、勤怠管理システムを導入して勤怠管理を行えば、社内業務を効率的に推進できるでしょう。
勤怠管理システムの導入における注意点

新しく勤怠管理システムを導入した場合、従業員の勤怠状況を正確に捉え、労務管理の改善や生産性を向上できるメリットが生まれます。しかし、導入するには、いくつかの注意点があります。法令遵守のために必要な項目もあるため注意しましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
法令遵守のために必要な項目
自社の就業マニュアルは法令に準拠したものか
新しく勤怠管理システムを導入する際には、就業マニュアルが法令に準拠しているかどうかを確認することが重要です。就業マニュアルが法令に準拠したものでなければ、企業は労働基準法違反と見なされる可能性があります。
就業マニュアルが法令に準拠したものであれば、自社の法律的な責任を明らかにすることができます。また、従業員に対して、明確なルールや方針を提供し、法的な義務を為し遂げることで、訴訟などのリスク軽減ができます。
就業マニュアルの変更にすぐ対応できるか
法改正や、自社の勤務ルールの変更などにより、就業マニュアルは適正に変更する必要があります。その際、勤怠管理システムへの変更が迅速にできないと、従業員の正確な勤務状況の把握ができず、労働管理や給与計算に影響が及びます。
法改正や勤務環境の改善のために、自社の就業規則を変更する場合は、変更に素早く対応できるシステムの導入が重要です。
就業マニュアルと勤務実態に乖離がないか
勤怠管理において、就業マニュアルと勤務実態に乖離がある場合、労働基準法違反のリスクや、人事評価に不平等が生じる懸念があります。就業マニュアルは、労働基準法を基準として作成されており、従業員と使用者が守らなければならないルールが定められています。
そのため、就業マニュアルと勤務実態に乖離があると、労働基準法に違反するリスクが高くなります。
勤務実態に即した勤怠管理を行えるか
従業員の自己申告による出退勤報告には、不確実さや不明瞭さが伴います。そのため、勤怠管理システムを導入する際に注目したいのが、実態に準じた勤怠管理ができるかといった点です。
例えば、ICカード打刻のほかにWeb打刻やPCログで出勤時刻が把握できたり、従業員が打刻修正をした場合でも、実際の打刻時間が上書きされずに記録として残ったりする勤怠管理システムであれば、勤務実態が客観的に把握できます。
以前は把握対象外だった管理監督者やみなし労働時間制で働く従業員も、労働安全衛生法の改正により対象となったため、管理漏れがないか注意が必要です。
管理者・従業員双方が使いやすいシステムか
ほぼ全社員が利用対象者となる勤怠管理システムでは、全員が快適に利用できるかどうかは非常に重要です。デモ機や無料トライアル期間などを利用して、管理画面の操作性・スマホでの動作性などを大まかに検証しておくことをおすすめします。
ただし、注意しなければならないのは、管理者だけの目線で使い勝手のしやすさを判断しないことです。社員が使いにくいシステムであれば、確実に打刻できなかったり、ログインのたびにストレスを感じたりしてしまいます。
社員数や部署数の多い大規模企業では、一部の部署で試験的に運用してから、本導入を検討することも選択肢の一つです。
まとめ

勤怠管理は、労働基準法や労働安全衛生法で定められた企業の義務で、労働者や会社を守ることが目的です。法律に沿った勤怠管理をして、労働環境の整備を行います。勤怠管理は使用者の義務であり、万が一違反と認められれば、罰則規定もあるため注意しましょう。
労働基準法は、1947年の制定以降、随時改正されています。2023年4月1日に改正され、時間外労働について割増賃金率が変更されました。それまでは、1日8時間、週40時間を超える割増賃金率は25%でしたが、改正後は月に60時間を超えた分は50%へ上げられました。
また、勤怠管理を行ううえで理解しておかなければならない労働基準法の重要なポイント(労働時間・労働時間の把握・年間休日総数・年次有給休暇の取得・60時間以上の残業など)があるため、法令を順守した勤怠管理を行いましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ