社内FAQとは|社内FAQの作り方や作成する際の注意点を解説

Check!
- 社内FAQの活用で、従業員からのよくある質問への対応を削減することができる
- 質問と回答の整合性が取れていないと、新たな疑問を発生させてしまう可能性がある
- FAQの情報量が多い場合は、FAQシステムを活用する方が利便性が高い
社内FAQとは、従業員からのよくある質問と回答を集約し、整理したものです。社内FAQを活用することで、従業員自身で疑問を解決でき、担当者の対応にかかる負担を軽減できます。本記事では、社内FAQを作るメリットや作り方、作成時の注意点などを解説します。
FAQとは

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略です。よく寄せられる質問や疑問をまとめた文書またはWebページで、しばしばWebサイトや製品のサポートセクションに設けられます。
FAQは、一般的な質問とそれに対する回答を提供し、ユーザーが疑問や問題を迅速に解決できるように作成・運用されます。ユーザーが必要な情報を探しやすくなることで、ユーザーサポートの負担軽減につながります。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
FAQとは
社内FAQとは
社内FAQは、企業内で従業員がよく尋ねる質問や疑問をまとめた文書やデータベースです。組織内の業務や方針・手続き・規定などに関する情報を包括し、従業員が疑問や問題を解決するためのリソースとして活用されます。
社内FAQは従業員の業務効率や情報アクセスを向上させ、新入社員のトレーニングや研修にも役立ちます。また、明確な情報提供とコミュニケーションの促進を通じて、組織内のコミュニティや協力関係を強化する際にも重要です。
FAQとQ&Aの違い
FAQとQ&Aはどちらも質問と回答を指しますが、細かいニュアンスの違いがあります。FAQは日本語で「よくある質問」を意味し、頻繁に尋ねられる質問や一般的な疑問に焦点を当てます。
一方、Q&Aは質問とそれに対する回答を指す言葉であり、頻度にこだわらず、あらゆる種類の質問と回答を行います。FAQは頻度の高い質問に焦点を当てたもので、Q&Aは質問と回答全般を指す用語です。
FAQとナレッジの違い
ナレッジは包括的な情報を含むデータベースやリソースのことを指します。組織内の情報共有と学習を支援し、問題解決や意思決定をサポートします。一方、FAQは「よくある質問」への簡潔な回答を提供するためのリソースです。
FAQは特定の問題に対処するのに適しており、ナレッジはより包括的で総合的な情報リソースとなります。

FAQとは、顧客や従業員からのよくある質問と、その質問に対する回答を集約したものです。FAQを活用することで、これまで有人で行っていた対応を削減することができ、業務が効率化されます。この記事では、FAQの種類や効果、システム導入のメリットなどを解説します。
社内FAQを作るメリット
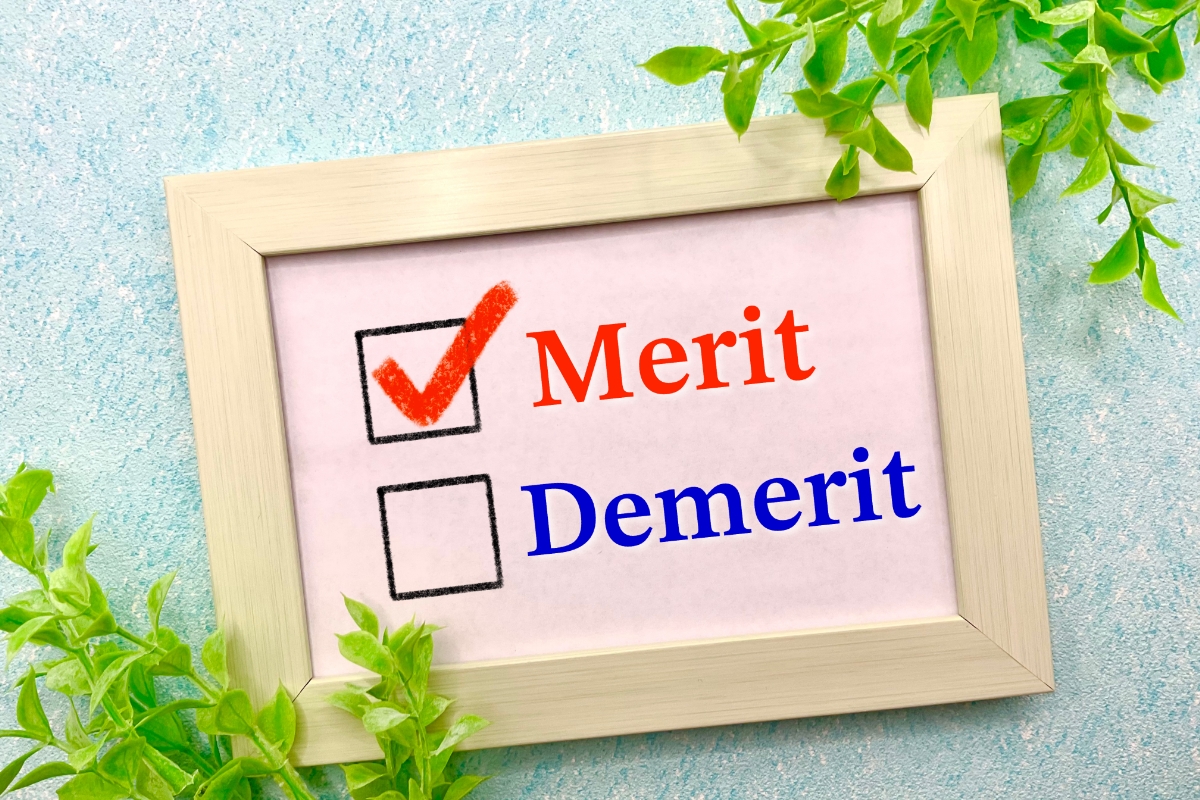
社内FAQの作成には多くのメリットがあります。従業員と組織にとってのスムーズな業務遂行と情報共有を可能にし、時間とリソースを節約できます。ここでは、社内FAQを作るメリットについて具体的に解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
社内FAQを作るメリット
ナレッジが蓄積されて属人化を防止できる
社内FAQの作成は、組織内のナレッジを蓄積し、個々の知識や経験に依存する「属人化」を防ぐために有効です。経験豊富な従業員が退職・移動した際にも、大事な知識が失われることなく組織内に留まります。
そして、蓄積されたナレッジを共有し、新入社員の教育や業務効率を向上させることが可能です。これにより、組織全体のレベルを引き上げ、持続可能な成長と進化を促進できます。
従業員からの問い合わせ対応を軽減できる
FAQによって、従業員は頻繁に発生する疑問についての情報に簡単にアクセスでき、素早く解決策を見つけられます。問い合わせやサポートにかかる時間や労力を削減し、サポート担当者は他の重要な業務に専念することが可能です。
また、FAQは一貫性のある情報を提供し、従業員間での情報共有を促進します。その結果、組織全体の効率性が向上し、迅速な問題解決にもつながります。
担当者が不在でも、疑問やトラブルを解決しやすくなる
社内FAQの作成で、業務時間外や担当者が不在の際にも、発生した疑問・トラブルを解決しやすくなります。FAQは常にアクセス可能であるため、従業員は必要な情報を手に入れるのに担当者の直接的な支援を待たずに済みます。
これにより、業務の中断や待ち時間が最小限に抑えられ、スムーズな業務フローの維持が可能です。従業員が疑問を簡単に解決できることで、生産性向上やストレス軽減につながり、組織全体の効率性を高められます。
対応のスピードアップで顧客満足度が向上する
社内FAQは顧客対応にも活用でき、担当者ごとに違った対応をしてしまうといったトラブルの防止につながります。問い合わせのたびに上司や他部署に確認するといった手間を削減し、ミスによるクレームを減らして顧客からの信頼性を高めることが可能です。
一つひとつの対応がスピードアップすることにより、一貫したサービスの提供で顧客満足度が向上します。なお、社内FAQに含まれるマニュアルを定期的に更新しておくと、古い情報を伝えてしまう事態を避けつつ、新人スタッフでも高品質な対応が可能になります。
教育にかける手間やコストを削減できる
従業員教育にかける手間やコストを削減できるのも、社内FAQの作成で得られるメリットです。FAQによって組織内の基本的な知識や手順を網羅することで、繰り返しの説明とトレーニングの必要性が軽減されます。
従業員は自分のペースで情報にアクセスし、必要な知識を習得できるため、教育にかける時間やコストを最小限に抑えることが可能です。そして、組織は生産性を向上させるための貴重なリソースを、他の重要な領域に割り当てられます。
社内FAQを作成・管理する方法

効果的な社内FAQの作成には、適切な方法とアプローチが必要です。ここでは、社内FAQを作成・管理する方法について解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
社内FAQを作成・管理する方法
ExcelやGoogleスプレッドシートを活用する
Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートを活用することで、簡単にテキスト情報を整理し、検索可能なフォーマットにまとめられます。質問とそれに対する回答を記入し、カテゴリーやキーワードで整理することで、従業員が必要な情報を素早く見つけられます。
これらのツールは、すでに社内で使われていることが多く、追加の費用やツールを扱うためのトレーニングにかかる負担が少ないです。無料かつシンプルで使いやすい方法で社内FAQを作成し、従業員の適切なサポートと知識共有につなげられます。
チャットボットを活用する
Webページ上など、ユーザーとやり取りができるチャットボットは、FAQシステムとして活用することも可能です。FAQデータをある程度収集していれば、そのデータをチャットボットに組み込むことで、簡単にFAQシステムとして活用できます。
チャットボットは会話形式であるため、自分で検索結果から欲しい情報を探すという手間が省けます。担当者に問い合わせるような感覚で利用できるのもメリットです。
中には、AIによる機能が搭載されており、使うほどに回答精度を高められるツールもあります。

FAQシステムとチャットボットの違い|向いている企業の特徴も解説
FAQシステムとチャットボットは、どちらも顧客の疑問に対して回答を提示するシステムですが、自社に合うシステムはどちらなのか分からない企業もあるでしょう。本記事では、FAQシステムとチャットボットの違いや、それぞれ導入が向いている企業の特徴を解説しています。
FAQシステムを導入する
FAQシステムはFAQの作成・運用に特化したソフトウェアで、情報量が多い場合や多くのユーザーにサービスを提供する際、利便性を高めるのに役立ちます。社内FAQを自作するよりも、より高度なFAQを作ることが可能です。
FAQシステムには、質問と回答のデータベースを効率的に管理できる仕組みが整っており、充実した検索機能も提供されているため、ユーザーが必要な情報にアクセスしやすくなります。FAQの整理や更新が簡単で、迅速な対応が可能です。
また、FAQシステムには分析機能が搭載されていることも多く、より具体的な課題やトレンドを把握でき、サポートの質向上にもつながります。情報量が多くなると予想される場合には、FAQの拡充と運用の効率化に向けたFAQシステムの導入がおすすめです。
社内FAQに特化した「社内FAQツール」も
FAQシステムには顧客向けのFAQを作成するためのもの、社内FAQを作成するためのもの、その両方に対応できるものがありますが、社内FAQに特化したツールであれば容易に社内FAQが作成できます。
こうしたツールには、社内FAQの構築に役立つテンプレートや、社内でFAQを活用するためのさまざまな機能が備わっています。あらかじめ社内FAQとしての仕組みが整っていれば、構築の工数も大幅に削減できるでしょう。
多くのツールが存在するため、機能や仕様、料金などを比較しながら自社に合ったツールを選定しましょう。

FAQシステムとは、よくある質問(FAQ)とその回答を作成・検索できることで、ユーザーからの問い合わせ件数を削減できるシステムのことです。本記事では、FAQシステムの導入を検討している方に向けて、おすすめのFAQシステムや導入時の注意点などを解説しています。
社内FAQの作り方

FAQは従業員の質問や疑念を解消し、業務をスムーズに進めるのに役立つ貴重なツールです。しかし、適切に作成・運用されないと十分な効果を得られません。ここでは、社内FAQの作り方を手順に沿って詳しく説明します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
従業員からの質問や疑問をリストアップする
社内FAQを効果的に作成するためには、まず従業員からの質問や疑問をリストアップする必要があります。従業員の間で頻繁に生じる質問や問題点を洗い出し、それに対する明確な回答や解決策を用意しましょう。
これにより、FAQが実際のニーズに合致し、従業員がより迅速かつ容易に必要な情報を見つけられるようになります。現場の声を収集し、それに基づいてFAQを整備すれば、需要のあるFAQを作り上げることが可能です。
収集した質問や疑問に対して回答を当てはめる
次に、収集した質問に対して正確で明快な回答を提供するため、さまざまな情報源を参照します。内部ドキュメント・社内規則・製品マニュアル・業界における最善の方法などを検討し、適切な回答を整理・記述します。
従業員がFAQを使いやすくするために、わかりやすく・簡潔で一貫性のある回答を提供することが重要です。
FAQページを作成・公開する
FAQページを作成・公開する際は、FAQを従業員が見つけやすい場所に配置します。社内のイントラネットや共有ドライブを活用したり、専用のFAQページを作成したりしましょう。
また、FAQ項目は緊急性や優先度の高いものから並べ、わかりやすいカテゴリーやキーワードで整理します。これにより、ユーザーは必要な情報を素早く見つけられます。
FAQの更新や改善を行う
FAQの公開後は、新たな質問や変更事項が生じた際に適宜更新を行います。具体的には、FAQの利用状況や従業員からのフィードバックを分析し、より有用な情報を提供できるよう改善点を特定します。
そして、新たな質問や課題が見つかった場合、それらをFAQに反映させます。また、FAQの明瞭さやアクセス性を向上させるため、わかりやすい表現やカテゴリー分けを検討し、必要に応じてリンクや検索機能の追加を行うことも大切です。
FAQの定期的な更新と改善により、企業の成長や変化に対して迅速かつ効果的に適応でき、FAQの価値を保てます。
社内FAQを作成する際の注意点

効果的なFAQを構築するには、いくつかの注意点が存在するため、それぞれを把握して従業員への適切な情報提供を行いましょう。ここでは、社内FAQを作成する際の注意点について解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
社内FAQを作成する際の注意点
公開前に質問と回答の整合性が取れているか確認する
社内FAQを作成する際、公開前に質問と回答の整合性を確認しておきましょう。質問と対応する回答が一貫していないと、混乱を招いたり、情報提供の信頼性が損なわれたりします。
そのため、各質問に対する明確かつ正確な回答を用意することが重要です。情報の一貫性を維持し、間違った情報をユーザーに与えないようにするために、公開前に綿密な審査と整備を行いましょう。
従業員側の使いやすさを重視する
社内FAQの作成では、従業員がスムーズに利用できるFAQを提供するために、検索機能を備え、キーワードを用いた迅速な情報アクセスを可能にします。また、FAQはカテゴリ分けし、トピック別に整理されていれば、ユーザーが目的の情報を容易に見つけられます。
さらに、どのユーザーも理解できるように、回答内容は専門用語を避けてわかりやすく表現し、必要な場合には用語の説明を添えましょう。
回答ボリュームにも注意が必要
FAQの利便性は、問題や疑問に対する答えを素早く見つけられることにあります。そのため、1つの質問に対する回答ボリュームがあまりに大きいと、利便性が損なわれてしまいます。特に、業務に関するFAQでは回答が複雑になりやすいため注意が必要です。
状況によって回答が複数ある場合や、説明が長くなりすぎる場合には、より細分化したFAQページを作って回答欄にリンクを掲載したり、別で用意されているマニュアルや資料のリンクを掲載したりして、FAQの回答自体がシンプルになるような工夫が必要です。
社内への周知とルールの設定をする
社内FAQの運用において、社内への周知とルール設定は欠かせないポイントです。まず、FAQの存在と使い方をすべての従業員に周知しましょう。具体的には、会議や社内メールでのアナウンス、社内ポータルへリンクの掲載などを行います。
また、ルールを設けてFAQの管理者を明確に指定し、更新頻度や内容の審査方法を定めなければなりません。例えば、「FAQの内容変更には最低2名の管理者の承認が必要」といった具体的なルールを設けることで、FAQの整合性を保ちつつ信頼性の向上につながります。
スモールスタートで運用を始める
社内FAQを導入する際は、スモールスタートから始めるのがおすすめです。スモールスタートは少数のユーザーまたは特定の部門でFAQの運用を開始し、その成果と課題を評価するアプローチです。
最初は一部の部署や従業員に限定して導入し、利用状況やフィードバックを収集しましょう。これにより、初期段階でのトラブルや問題の発見を容易にし、必要な修正や改善を行うことができます。
また、少ないFAQ数で始めることで導入時にかかる工数も削減でき、大規模な運用に向けて柔軟な体制を整えられます。
FAQの活用を促進して社内に定着させる
社内FAQは作成するだけでは意味がなく、従業員に積極的に使ってもらうことが重要です。社内にFAQの存在を周知するのはもちろん、研修でFAQの使い方を解説したり、定期的に社内ポータルなどで案内したりすることで、利用を定着させられます。
また、スマートフォンやタブレットといった端末からも見やすいレイアウトにし、各業務システムからも直接FAQにアクセスできるようにしましょう。
その他、FAQでは解決しなかった場合の対応も明確にしておき、利用状況からどの程度役立っているのかを定期的に評価するのがおすすめです。
まとめ

社内FAQは、組織内でよく寄せられる質問とそれに対する回答をまとめたリソースです。社内FAQの作成によってナレッジが蓄積され、従業員間で共有しやすくなり属人化の防止につながります。また、サポート部門の負担軽減も可能です。
ただし、FAQを公開する前に質問と回答の整合性を確認し、情報の正確性を保証しなければならず、ユーザーエクスペリエンスを考慮し、従業員にとって使いやすいものへと更新・改善を続ける手間がかかります。
なお、社内FAQはスモールスタートで段階的に展開していけば、失敗を防ぐことが可能です。組織の成長と業務の効率化に向け、明確かつ正確な回答を用意しながら、社内FAQを適切に運用していきましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

