車両管理規程とは?必要性や記載すべき内容、注意点などを解説

Check!
- 車両管理規程とは、従業員が業務中に車両を使う際に企業が定めたルールのことである
- 車両管理規程には、事故発生時の費用負担や事故が起きた際の対応などを記載する
- 従業員が規程を違反した場合、就業規則に明記されている場合のみ罰金を課せられる
車両管理規程とは、従業員が業務中に車両を使う際に企業が定めたルールのことです。車両管理規程を作成することで、事故による損害の防止にもつながります。本記事では、車両管理規程の必要性や記載すべき主な内容、違反した場合の罰則に関する注意点について解説します。
車両管理規程とは

車両管理規程とは、企業が従業員に対し、社用車の利用方法を定めたルールです。主な目的は、従業員が社用車の運転中に交通事故を起こした場合、それによって発生するさまざまなリスクを回避することです。
車両管理規程が適用されるのは、物流トラックやバス・タクシーといった緑ナンバーの車です。また、白ナンバーの車であっても、営業・送迎・簡単な配送といった業務で利用される場合は、車両管理規程の対象となります。
また、業務に利用するのであれば、原則として会社購入の車両・レンタカー・従業員のマイカーにかかわらず、車両管理規程が適用される点も留意しておきましょう。
車両管理規程の作成が必要な理由
車両管理規程の作成が求められる理由は、従業員の運転中の交通事故を防止し、安全な運転を担保するためです。さらに、車両管理規程の作成は、以下の2つの法律を守るために必要です。
民法第715条「使用者等の責任」
民法第715条は、「使用者等の責任」について定めた法律です。従業員が不法行為をし、第三者に損害を与えた場合、会社(雇用主)が損害賠償の責任を負う旨を定めています。
例えば、従業員が社用車で交通事故を起こし、第三者に怪我を負わせた場合が該当します。事故を起こした従業員はもちろん、会社もその損害賠償を行わなくてはなりません。
ただし、車両管理規程を定めておけば、日頃から交通事故を防止するための取り組みを行っていたと見なされ、使用者等の責任を問われない可能性があります。損害賠償は高額になりやすいため、金銭的なリスクを避ける上でも車両管理規程の作成が必要です。
また、車両管理規程を作成・周知することで、従業員に交通安全の意識が芽生えやすくなります。交通事故発生後のリスクを避けるだけでなく、そもそも交通事故を起こさないようにするためにも、車両管理規程は重要なルールです。
道路交通法第74条の3「安全運転管理者の選任」
道路交通法第74条の3は、「安全運転管理者の選任」についての法律です。業務用車両を5台以上保有する会社に対し、安全運転管理者を設置する旨を定めています。11人乗り以上の車両を1台以上保有する会社にも適用されます。
安全運転管理者とは、従業員の道路交通法を遵守し、安全な運転を行うように監督する者です。例えば、ながら運転の禁止や、運転前のアルコールチェックが安全運転管理者の業務です。具体的な業務内容については、車両管理規程に明示しておく必要があります。
従業員が道路交通法に則って安全な運転を行うためにも、会社は車両管理規程の作成と安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
車両管理規程の対象になる車両

通勤や業務上で利用するすべての車両は、車両管理規程の対象となります。ここでは、車両管理規程の対象になる主な車両と、規定すべきポイントについて説明します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
車両管理規程の対象になる車両
社用車
企業が社用車を購入した場合は、運転者に対する責任を明確にしておきましょう。車両管理規程として、社用車を業務以外の目的に使用しないこと、車両管理台帳の作成、事故時の対応、社用車の整備点検や修理における明示などが必要になります。
さらに、事故時の対応について明確にしておくことにより、余計なトラブルを避けつつ、運転者の安全への意識を高められます。
個人保有の自動車(マイカー)
通勤や業務に従業員個人保有の自動車(マイカー)を利用する場合、交通事故時の会社側の賠償負担が大きくなりがちです。こういったリスクを避けるためにも、マイカーの利用方法について車両管理規程に記しておく必要があります。
- 使用頻度
- 使用範囲
- 使用時間
- 使用条件
上記の項目に加え、マイカーでの交通事故時の損害賠償や管理責任についても明記しておきましょう。なお、通勤時の事故は、労災認定される可能性があります。事前に、任意保険の加入状況の確認・保険証券の提出を定めておくのがおすすめです。
なお、マイカーとしての利用はトラブルが起こりやすいため、原則禁止が望ましいです。通勤・業務でのマイカーの使用を禁止する場合は、その旨を車両管理規程に記載しましょう。
レンタカー
使用頻度によっては、コスト削減を目的にカーリースやマンスリーレンタカー、単発のレンタカーを使用する場合があります。特に、単発のレンタカーの場合は、別途ルールを設けることが必要です。
レンタカーの使用についての車両管理規程を定める際、レンタカー使用の許可基準やレンタカーを使用する際の届出を明確にしておきましょう。
自転車
自転車も軽車両として車両に該当します。そのため、自転車通勤を認める場合は、車両と運転者の管理が必要になります。
また、自転車の使用に関して車両管理規程を定める場合は、自転車通勤の許可基準や自転車通勤の届出、業務と私用の明確な区分、安全教育、自転車通勤に関するルール作りをしましょう。自転車であっても、事故を起こした際の適切な対応でトラブルを防げます。
車両管理規程を作成する重要性

車両管理規程の作成は、事故リスク・損害の防止や台帳の適切な管理のために重要です。それぞれの内容を解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
車両管理規程を作成する重要性
事故リスク・損害の防止
車両管理規程は、従業員の交通事故によるリスクを回避するために重要です。従業員が交通事故を起こし、第三者に損害を与えた場合、会社には損害賠償を行う義務があります。損害賠償が高額であるほど、当然ながら会社の金銭的負担も大きくなります。
また、社用車で交通事故を起こした場合、それだけで会社の社会的信頼は低下するでしょう。こういったリスクを避けるためにも、車両管理規程を定め、従業員の交通事故を防ぐことが大切です。
コスト削減につながる
適切なコスト管理を行うことで、燃料費や維持費を削減し、経営の効率化を図れます。例えば、エコドライブの推奨や燃費効率の良いルートの選定、給油場所・ルートの統一によって無駄な燃料消費を減らし、不必要なアイドリング・遠回りもなくすことが可能です。
また、定期的な車両メンテナンスを行い、突然の故障を防ぐことで修理費も削減できます。利用者に対して走行距離や整備履歴の記録を徹底させ、タイヤの空気圧管理とエンジンオイル・ブレーキの点検により、未然に故障を防ぎながら車両の寿命を伸ばすことが可能です。
台帳の適切な管理が可能
車両管理規程は、台帳を適切に管理する上でも重要です。社用車を保有する会社には、次のような台帳の記録と管理が求められます。
- 運転者台帳
- 車両管理台帳
- 運転日報
- 日常点検記録
- アルコールチェック記録表
台帳の記録・管理を徹底するためにも、車両管理規程にその旨を盛り込んでおく必要があります。
車両管理規程に記載するべき主な内容
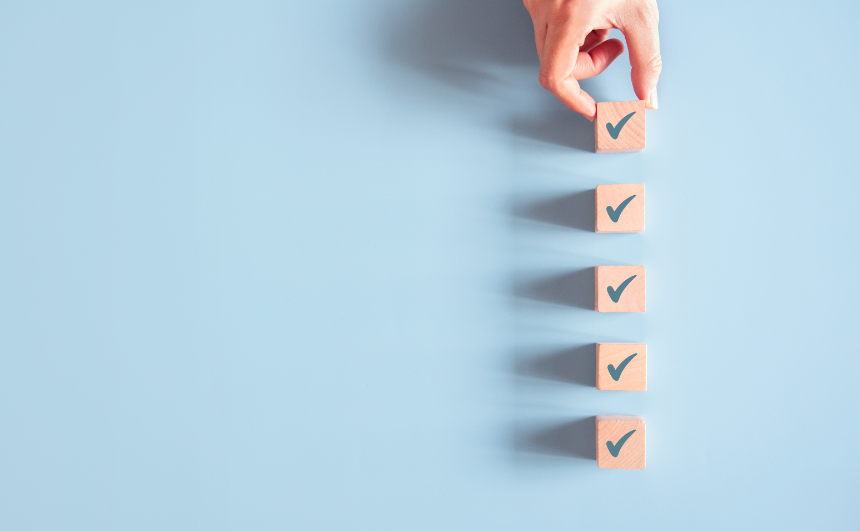
車両管理規程を作成する際は、少なくとも次のようなポイントを盛り込むことが大切です。ここでは、各ポイントの内容を解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
車両管理規程に記載するべき主な内容
安全運転管理責任者の選任
安全運転管理者とは、従業員が道路交通法を遵守して運転するように監督する者です。道路交通法は、社用車を5台以上保有する会社に対し、安全運転管理者の選任を義務付けています。
車両管理規程には、安全運転管理者を選任する旨を明確に記載しておく必要があります。これにより、企業として道路交通法を遵守する意思を示せます。
なお、安全運転管理者は、選任後15日以内に公安委員会に届け出ることが義務付けられています。届出を怠ると、最大で2万円の罰金が科されるため注意しましょう。
車両管理台帳の作成
車両管理台帳とは、社用車を個別に管理するための台帳です。車両を特定するための項目や、車両の状況を把握するための項目を記載しておく必要があります。
例えば、次のような項目の記載が必要です。
【車両を特定するための項目】
- 車名
- 車種
- 型式
- ナンバー
- 車体番号
- 色
【車両の状況を把握するための項目】
- 車検日
- 点検日
- 業者名
- 車検整備箇所
- 保険の有効期限
車両管理台帳は、社用車を適切に管理していることを証明する台帳です。これらの台帳の記録・管理を徹底するためにも、車両管理規程に必ず盛り込みましょう。
運転者台帳の作成
運転者台帳は、社用車の運転許可を得た従業員を管理するための台帳です。車両管理台帳とセットで管理することが望ましいです。
運転者台帳には次のような項目を記載します。
- 台帳の作成年月日
- 運転者の氏名
- 運転者の性別
- 運転者の住所
- 所属部署
- 雇入の年月日
- 運転歴
- 事故・違反歴
- 免許の更新時期
- 写真(運転者台帳作成6ヶ月以内に撮影したもの)
運転者台帳と車両管理台帳を連携させることで、交通事故発生時も適切な対応を取りやすくなります。また、企業として運転者の管理責任を果たしていることを証明するためにも、運転者台帳の作成が必要です。
事故発生時の費用負担
車両管理規程には、社用車で交通事故・違反を起こした場合の従業員と会社の費用負担の仕方を記載します。費用負担を明確にすることで、会社の損失を可能な限り減らす狙いがあります。
また、交通事故発生後に費用負担をめぐって従業員と会社間でトラブルを起こさないためにも、あらかじめルールを決めておかなければなりません。
負担の仕方に決まりはありませんが、交通違反時の負担は従業員が負い、交通事故時の負担の責任は会社が持つことが一般的です。
ただし、交通事故の場合でも、従業員に明らかな過失がある場合は異なる処置が適切な場合があります。想定される例外についても、明確に記載しておきましょう。
車両の点検・整備
車両の点検・整備についても車両管理規程に盛り込む必要があります。車両の点検・整備についての事項としては、次のようなものがあります。
- 車検
- 定期点検
- 日常点検
これらを定期的に行い、社用車の状態を常に良好に保つことで、従業員の安全と事故予防につながります。点検・整備を徹底するためにも、車両管理規程に明示しておきましょう。
マイカーの使用
通勤や業務に従業員個人保有の自動車(マイカー)を利用する場合、交通事故時の会社側の賠償負担が大きくなりがちです。こういったリスクを避けるためにも、マイカーの利用方法について車両管理規程に明確に記しておく必要があります。
- 使用頻度
- 使用範囲
- 使用時間
- 使用条件
併せて、マイカーでの交通事故時の損害賠償や管理責任についても明記しておきましょう。なお、通勤時の事故は、労災認定される可能性があります。これに備えて、任意保険の加入状況の確認・保険証券の提出を定めておくと良いでしょう。
マイカーの利用はなにかとトラブルが起こりやすいため、原則禁止が望ましいです。通勤・業務でのマイカーの使用を禁止する場合は、その旨を車両管理規程に記載しましょう。
事故発生時の対応
事故が発生した場合の対応方法についても、車両管理規程に明示しておきます。事故後は冷静な対応が難しいことも多いため、適切な対応方法をあらかじめルール化しておくことが大切です。
例えば、事故報告・事故処理のやり方、事故に関する責任の所在や罰金等の負担について明確にしておきましょう。さらに、事故発生後の再発防止策にも触れておくことが望ましいです。
車両管理規程を違反した場合の罰則における注意点

車両管理規程に違反した場合の罰則を定めておくと、従業員の意識も高まりやすくなります。ただし、車両管理規程の罰則にもルールがあるため、次のような点に注意しましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
車両管理規程を違反した場合の罰則における注意点
従業員への罰金は法律上NG
労働基準法第16条は、企業が、車両管理規程に違反した従業員に対し、罰金を科すことを法律違反としています。ただし、条件を満たした形であれば、違反時に罰則を科すこともできます。
車両管理規程や就業規則に明記する
車両管理規程に違反した従業員への罰金刑は、原則NGです。ただし、金銭徴収の目的が会社の秩序を維持するためであり、かつ車両管理規程と就業規則に明記されていれば、労働基準法第91条の範囲において減給を科すことが可能です。
罰金ではなく、減給という形を取ることがポイントです。減給以外に、降格・厳重注意といった罰則を科す企業も多いです。どのような罰則を科すにしても、その旨をあらかじめ車両管理規程・就業規則に明記しておきましょう。
罰則だけでなく再発防止策も強化する
罰則の目的は単に処罰をすることではなく、既定の遵守を促して事故やトラブルを防ぐことにあります。そのため、罰則主義を掲げるのではなく、教育・指導を基本とし、再発防止策と合わせて考えることが大切です。
事故・違反が発生した後は原因を特定・分析し、ルールの認識不足がなかったか、意識の低さ・管理体制の不備が要因ではなかったかなど、背景を調べてそれに適した対策を講じましょう。再発防止策の強化についても、事前にルール決めしておくのがおすすめです。
まとめ

車両管理規程は、企業が従業員に対し、社用車の利用方法を定めたルールです。運転者の道路交通法の遵守・安全な運転を確保する目的があります。
車両管理規程を作成することで、交通違反や交通事故時の企業の損害負担軽減に期待できます。また、車両管理台帳や運転者台帳といった各種台帳の記録・管理を徹底する際にも、車両管理規程の作成は重要です。
車両管理規程に違反した場合、原則として従業員に罰金を科すことはできません。車両管理規程の作成方法や違反時の対応を理解し、社用車を適切に運行しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

