VDIとは?機能や種類、メリット・デメリットをわかりやすく解説
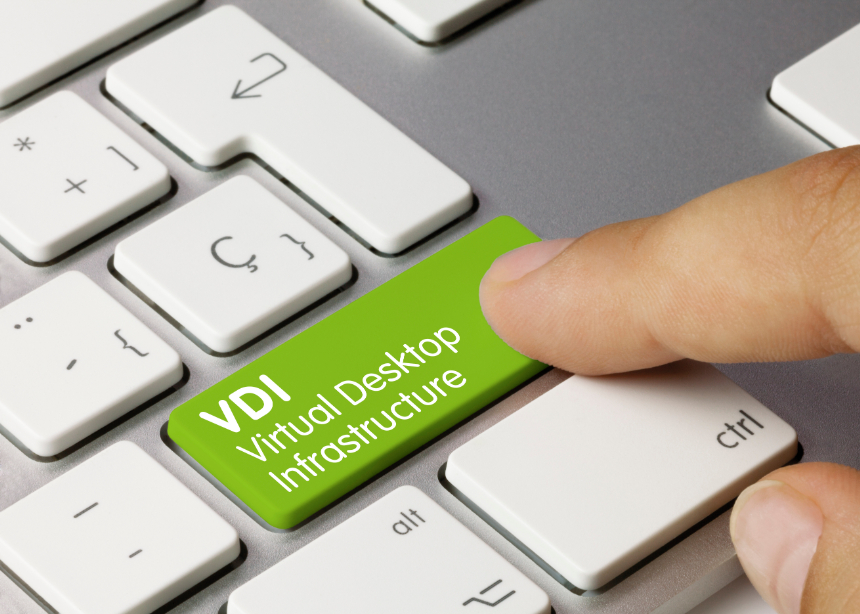
Check!
- VDIとはデスクトップ環境を仮想化させて、サーバー上に集約・稼働させる仕組みのこと
- VDIの導入でセキュリティ対策の強化やコスト削減、リモートワーク対応化に繋がる
- VDI製品導入の際はニーズに合った導入形態を選び、適切なサイジング・動作検証を行う
VDIとはデスクトップ環境を仮想化させて、デスクトップ環境をサーバー上に集約・稼働させる仕組みのことです。いくつかの機能・種類があり、導入には注意点もあります。本記事では、VDIの種類やメリット・デメリット、製品・サービスの選び方をわかりやすく解説しています。
VDI(仮想デスクトップ基盤)とは

VDI(仮想デスクトップ基盤)とは、「Virtual Desktop Infrastructure」の略称で、仮想化技術を用いてPCの仮想デスクトップ環境をサーバ上に作り、サーバー上のデスクトップ環境で業務を行う仕組みのことです。
ネットワーク経由でサーバー上の仮想デスクトップ環境に接続すれば、遠隔地にいてもオフィスのデスクトップ環境で業務を行えます。ローカルの端末にデータやアプリケーションを保存する必要がないため、VDIの導入によって情報漏洩のリスクも軽減できます。
VDIの仕組み・機能
VDIの仕組みは、手元にあるPCでサーバーやデータセンターにアクセスし、遠隔操作をするイメージです。企業で業務を行うPCには、その端末ごとにOSとソフトウェア、データが保存されているのが一般的です。
しかし、VDIでは、ユーザーがサーバー上に構築された仮想デスクトップにアクセスして、そこにあるソフトウェアやデータを使用します。計算処理もサーバー上で行われ、処理結果だけが端末に転送されるため、自宅や出先など会社以外の場所でも作業が可能になります。
VDIとシンクライアントの違い
VDIとシンクライアントは、使い方が難しく混在しがちな言葉ですが、示す意味は異なります。シンクライアントは、広義ではデスクトップ仮想化の技術そのものを表し、狭義には仮想デスクトップにアクセスする、必要最小限の機能を備えた端末を意味します。
対して、VDIは、広義では仮想デスクトップ環境を表し、狭義にはシンクライアントの実装方式の1つを意味する言葉です。しかし、最近はVDIがシンクライアントの実装方式に選ばれることが多いため、デスクトップ仮想化をVDIと表現するケースも増えています。
VDIとリモートデスクトップの違い
VDIと同じように、リモートデスクトップでも自社内のPCやサーバー、クラウドサービス上にデスクトップ環境を作り、遠隔地からアクセスして業務が行えます。しかし、VDIとリモートデスクトップができることには違いがあります。
VDIは、利用者一人ひとりに仮想デスクトップを用意できますが、リモートデスクトップはサーバーやパソコンを複数人で共有する使い方です。また、リモートデスクトップの特徴として、ユーザーごとに作業環境を整えたり、1人が長時間作業することは不可能です。
そのため、サーバーの利用頻度が低く、ユーザーの作業環境が似ている状況でないと、上手く機能しない場合があります。出張先やリモートワークなど、従業員がそれぞれの場所から各々の作業を行う場合は、VDIが適しています。
VDIの種類・実施方式

VDIには、いくつかの種類・実施方式があります。導入によって望む効果を得られるように、それぞれの違いをしっかり確認して、自社に合ったものを選びましょう。
ここからは、VDI方式、ブレードPC方式、HDI方式、SBC方式、DaaS方式のVDI実施方式5種類を解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
VDIの種類・実施方式
VDI方式(仮想PC方式)
VDI方式は、サーバー上に複数の仮想デスクトップを作り、クライアント端末から接続する方式を言います。VMware vSphere、Microsoft Hyper-Vなどでサーバー上に仮想デスクトップを作り、それぞれにOSをインストールします。
VDI方式は、1人に1台のパソコンを用意して作業を行えるような環境を整えられる点がメリットです。これによって、ユーザーごとに独立した作業環境を用意でき、端末ごとにインストールするアプリケーションも選択できます。
ただし、Windows OSを使用する場合は、ローカル端末ごとにVDA(Virtual Desktop Accessライセンス)ライセンスが必要になります。ユーザーの利用するローカル端末ごとにライセンス契約をしなければならないため注意しましょう。
ブレードPC方式
ブレードPCとは、オフィスで使用されるようなパソコンとは違い、パソコンのCPU・メモリ・ストレージなどをブレードという基盤に取り付け、そのブレードを集約して集中管理を行うパソコンを指します。
大企業や大人数の学校などで使用され、サーバールームにブレードPCを集約して設置することで、省スペース化・省電力化を図れます。そして、管理コストの削減やセキュリティ面での強化、運用の効率化にも期待ができます。
また、この特長を活用したブレードPC方式は、VDI方式と似ているものの、サーバー上で仮想化されたパソコンを複数使用するわけではありません。環境が独立しているため、使用者の増加によって処理性能が低下することがないのがメリットです。
しかし、機能・操作の柔軟性や自由度が高い一方で、ブレードPCとは別に利用者数分のパソコンを用意する必要があります。つまり、企業によっては導入費用・運用費用が高額になる恐れがあり、この点は大きなデメリットとなります。
HDI方式(ホスト型デスクトップインフラ方式)
HDI(Hosted Desktop Infrastructure)方式は、社員が使う1台のローカル端末に対して、1台のサーバーやPCを用意し、仮想デスクトップを作成します。複数PCと共有しないためサーバーに余裕ができ、遠隔地からでも安定した操作ができる点が魅力です。
しかし、HDI方式はVDI方式のように、サーバー上に複数の仮想デスクトップを作成し、サーバーを共有して使用する方式ではありません。したがって、ユーザーごとにサーバーやPCを用意しなければならず、コスト面での負担が増えてしまう点はデメリットです。
SBC方式(サーバーデスクトップ共有方式)
SBC(Server Based Computing)方式は、サーバーにOSやアプリケーションを用意し、複数人で共有して使用する方式です。仮想デスクトップを作らず、クライアント端末からホストとなるPCやサーバーにアクセスするため、コストが比較的かからない点が魅力です。
また、仮想デスクトップを作成するときのように、それぞれにライセンス費用は発生しません。しかし、パソコンを共有して使うことになるため、自由度は低く、ユーザーごとに利用環境を整えることはできません。
DaaS方式(パブリッククラウド方式)
Daas(Desktop as a Service)方式は、クラウドサービス提供事業者が構築した環境でVDI方式を利用します。VDI用の物理サーバーを自社設置する必要がないため、初期費用が安くなる点が魅力です。
Daas方式は、クラウド上に作成する仮想デスクトップであり、仮想デスクトップ上で全ての作業を完結できます。そのため、自社にサーバーを設置した場合と、ほとんど変わらないパフォーマンスでの作業が可能です。
また、インターネット接続できる環境があれば、どこの端末からもデスクトップ環境を利用でき、データの保存にも対応しています。一方で利用環境はITインフラに依存するため、ユーザー数が増えると動作が重くなるという欠点も持っています。
VDIのメリット

VDI導入のメリットは大きく、システムの導入でセキュリティ対策の強化やコスト削減を期待できます。導入後、VDIを運用しているイメージを掴むため、VDIの持つメリットを3つ紹介します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
VDIのメリット
セキュリティを強化できる
VDIの導入は、セキュリティ対策とBCP(事業継続計画)対策の強化に期待できます。VDIは、社員がクライアント端末から、サーバー上の仮想デスクトップにアクセスして業務を行い、実際に利用するアプリケーションやデータはサーバー上に保存される仕組みです。
つまり、実際に社員が利用する手元の端末には情報が残らないため、ウィルス感染や紛失・盗難が起きた場合も情報漏洩を抑えられます。情報漏洩は企業の信頼性に悪影響を与え、法的責任を問われる恐れもあるため、情報漏洩のリスク軽減は大きなメリットと言えます。
また、VDIは台風や地震などの災害が起きた場合、業務継続が可能であるのもメリットです。自宅からネットワークを介して仮想デスクトップに繋げられるため、万が一社員が出社できない事態になっても事業を継続できます。
端末管理業務の効率化とコスト削減
VDIの導入は、管理業務の効率化とコストの削減にもつながります。VDIでは、社員一人ひとりがPCを所持し、管理・運用している従来の方式のように、各PCごとにセキュリティソフトのインストール・アップデートを適用するといった作業は不要です。
ソフトのインストール、OSのアップデートはサーバー側で一括管理できるため、ユーザーと管理者、両者の負担を減らし、管理業務を効率化できます。さらに、企業によっては負担が大きいハードウェア購入のコストも減らせます。
また、VDIはサーバー上でアプリケーションの演算処理を行い、結果をクライアント端末に返して表示する仕組みのため、社員が使うPCは高スペックである必要はありません。このように、作業品質の向上に加えて、大きなコストの削減にも期待できます。
リモートワークに対応
VDI環境の整備は、リモートワークの推進にもつながります。あらゆる場所で仕事ができるようになるVDIは、台風や地震などで社員がオフィスに出勤できない災害時にも、事業の継続が可能で、働き方の多様性ももたらしてくれます。
つまり、VDI環境が整備されていれば、社員は遠隔地においても仮想デスクトップにアクセスでき、オフィスにいるときと同様のデスクトップ環境で、場所にとらわれず業務が行えます。こういった準備は、緊急時・いざという時の対応策にもつながります。
VDIのデメリット
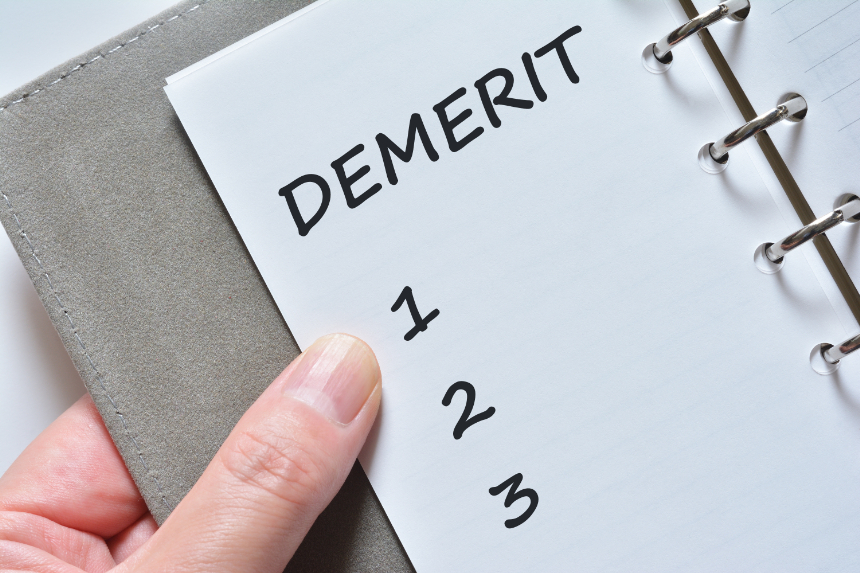
VDIは大きなメリットをもたらしてくれますが、デメリットも持ち合わせています。ここからは、VDIのデメリットを2点紹介します。VDIを導入して上手く運用するために、デメリットも確認しておきましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
VDIのデメリット
ネットワークに依存してしまう
VDI環境の導入によって、ネットワークへの依存が高くなる傾向があります。VDIは、サーバー上の仮想デスクトップを利用するため、ネットワークに接続できる環境が必要であり、すべての処理はネットワークを通じてサーバー上で行われます。
そのため、ネットワークへの接続が不安定な場合や、ネットワークが切断されてしまった場合は業務を遂行できなくなってしまいます。つまり、災害時だけでなく、急な通信環境のトラブルに対しても、柔軟に対応できるような環境づくりが必要です。
VDIの導入を検討する際には、評価の高い安定したインターネット回線の契約や、なるべく接続の途切れないルーターの用意などの環境整備についてもしっかりと確認しましょう。
サーバーへの負荷が高い
VDIはサーバー上に複数のデスクトップを集約し、すべての処理をサーバーが行うシステムであるため、ユーザー数が多いことでアクセスが集中します。その場合、ネットワーク帯域が圧迫され、サーバーへの負荷が高くなってしまいます。
ネットワーク帯域が圧迫されると、スムーズな処理ができなくなり、社員の業務に支障をきたします。したがって、管理者はユーザーの業務に支障が出ないようにサーバーを管理する必要があるため、サーバーの保守・管理担当者への負担も大きくなります。
自社にサーバーの設置を考えている場合は、サーバーの保守・管理体制を整える必要があります。また、外部サービスを利用する際は、安定したクラウドサービスを選定するとよいでしょう。
VDIの導入がおすすめの企業

VDIの導入は、働き方改革を進めたい企業やBCP対策に対応したい企業に特におすすめであり、大きなメリットを得られる可能性が高いです。ここからは、これらの企業におすすめの理由について解説します。
働き方改革を進めたい企業
VDIは、働き方改革を進めたい企業に適しています。働き方改革とは、働く人々が個々の事情に応じて多様な働き方を選べる社会を目指すための改革です。
VDIを企業に導入することで、会社のパソコンでしかできないような仕事も、自宅のパソコンや外出先のタブレットなどから作業ができるようになります。効率的にリモートワークに対応できるため、育児や介護などで出社が難しい従業員も自宅での作業が可能です。
また、営業など出先での業務が多い企業では、出先から職場に帰らないと処理できない業務もあり、結果として従業員の残業時間が増えてしまう課題もあります。VDIによって、このような業務もその場で処理できるため、移動の手間が省けて残業時間削減に期待できます。
VDIは、パソコンにデータを保存しない仕組みであるため、情報漏洩の発生も最小限に抑えられます。このようにVDIを導入することで、セキュリティリスクを抑えながらどこからでも業務を進められるため、働き方改革の推進におすすめです。
BCP対策をしたい企業
BCP(Business Continuity Plan)対策とは、日本語では「事業継続計画」を意味し、災害や事故などの発生時に、被害を最小限に抑えて速やかに復旧するための計画を指します。
地震や台風などの災害はいつ発生してもおかしくないため、企業はリスクに備えて社内のデータを管理することが求められます。VDIは、災害などで万が一オフィスが使えない状況になった際でも、自宅や避難先のパソコンなどから作業環境にアクセスできます。
また、パソコンにデータを保存せず、サーバーに情報を保管する仕組みのVDIなら、パソコンの故障や電源が落ちた場合も、サーバーが無事である限りデータが消失するリスクを防げます。
災害や事故などが発生した場合でもVDIを導入しておくことで、データの安全性を確保し、迅速な業務復旧に繋げられます。したがってBCP対策に対応したい場合は、VDIは有効な方法と言えます。
VDI製品・サービスの選び方

各社が提供するVDI製品やサービスにはさまざまな種類があり、何を基準に選べばよいのか、判断に迷うことがあります。よって、ここからはVDIサービス・製品選定の際に役立つ、選び方のポイントを解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
VDIサービス・製品の選び方
導入目的を明確にする
VDIを導入する際には、導入目的を明確にしましょう。VDIサービスや製品は、セキュリティ対策が強固、サーバーが堅牢、環境構築が容易など、提供する事業者によって持つ強みが異なります。
自社が情報漏洩対策を重視するのか、リモートワークを推進したいのか、出張や外出の多い社員の利便性を向上させたいのかなど、導入目的にあった製品やサービスを選びましょう。これによって、導入が失敗するリスクを防げて、費用対効果の高い運用に期待できます。
導入形態を確認
VDIには、自社でサーバーを用意するオンプレミス型と、クラウドサービスを利用するクラウド型の2種類あります。
カスタマイズ性の高いオンプレミス型、手軽に素早く環境構築できるクラウド型、2つにはそれぞれの強み・特徴があるため、自社に合った導入形態を選びましょう。
オンプレミス型
オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置するため、ユーザーごとの環境構築も自由にでき、カスタマイズ性の高さやセキュリティが強固な点が魅力です。さらに、セキュリティ対策をしっかりと行っていれば、情報漏洩のリスクも低くなります。
しかし、オンプレミス型は自社内にサーバーを設置する必要があるため、最初に機器の購入費がかかります。また、仮想デスクトップ作成にはOSのライセンス購入費も上乗せされるため、導入費用は高額になりやすい点に注意しましょう。
クラウド型
クラウド型は、自社内にサーバーを設置する必要がないため、手軽にVDIを導入できる点が魅力です。サーバー設置のために機器やライセンスの購入費用がかからないことで、初期費用も抑えられるため、コスト面が気になる企業にもおすすめです。
環境の管理・保守はサービス提供事業者が行うため、VDI運用の負担も少なく済みます。さらに、クラウド型は環境の変化にも柔軟に対応できる点もメリットです。
サービスは少人数から利用可能で、その後人員が増えた場合にもVDI利用者を比較的簡単に増やすことができます。ただし、ベンダーが提供する環境を利用するため、セキュリティ対策が依存しやすかったり、カスタマイズの自由度が低い点に留意が必要です。
対応OSを確認
自社の利用している端末が、VDI製品やサービスの端末・OSと対応しているかも確認しましょう。外出先や出張先、ミーティングで便利に使えるandroid端末やiPadからVDIを利用したい場合は、端末が対応しているサービスを選ぶ必要があります。
Mac OSやLinuxでVDIを利用したい場合は、OSが対応しているVDI製品やサービスかどうかの確認も必要です。各社が提供するVDI製品やサービスは、Windows OSに対応していますが、それ以外のOSには対応していないケースがあるため注意しましょう。
動作スペックの柔軟性を確認
VDI導入の際は、動作スペックの柔軟性も確認しましょう。オフィスなどの事務作業をする社員用の仮想デスクトップと、重い描画処理、計算処理をするエンジニア用仮想デスクトップでは、必要とするスペックが異なります。
仮想デスクトップを快適にユーザーが利用できるかどうかは、CPUやGPU、メモリサイズ、ストレージの速度に依存します。つまり、それらの性能不足によって作業の快適性が損なわれるため、部署によってスペックを変更できるVDIサービスを選びましょう。
VDI導入の注意点

VDIは大きなメリットをもたらしてくれるシステムですが、導入に際して確認しておきたい注意点もあります。ここからは、システム導入を成功に導けるよう、VDI導入に際しての注意点を解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
適切なサイジング・動作検証を行う
VDI導入の際には、適切なサイジングが必要です。サイジングを誤ってリソースが不足すると、処理速度や反応速度の著しい低下が起こり、作業環境は極端に悪化します。そして、費用対効果にも大きな影響を及ぼすため、導入前にはしっかりとサイジングを行いましょう。
相対的なコストの削減を目指すことはもちろんのこと、快適な作業環境の整備は、社内品質向上・業務の効率化にもつながります。システムの導入を成功させるために適切な動作検証を行い、徹底的なリソースのサイジングも実施しましょう。
影響範囲の大きくない業務から運用を開始する
VDI導入の際は、影響範囲の大きくない業務から運用を開始しましょう。どのような業種でも新規システム導入時には、トラブル発生は十分に起こり得ることであり、VDI導入時にも変わりはありません。
影響範囲の少ない業務から導入を始めると、万が一不具合や障害が起こった場合にも被害は最小限に食い止められます。例えば、定例業務のみや特定の部署のみなど、小規模運用からスタートし、設定や運用方法を学んだうえで、VDIを全体の業務へと広げていきましょう。
障害時の対応を考えておく
ネットワークやサーバーに障害が発生した際の影響を交えて、障害時の対策も考えておきましょう。VDIは、サーバーにネットワーク経由でアクセスして業務を行うため、ネットワークやサーバーに障害が発生すると業務はストップしてしまいます。
そのため、予備のサーバーを設置したり、ネットワークの代替手段を用意しておくなど、事前に対策を講じることが重要です。これらの対策によって、緊急時にも慌てることなく適切な対応ができ、業務の停止や被害の拡大を防げるでしょう。
まとめ

VDIは、サーバー上に作成した仮想デスクトップ環境にクライアント端末からアクセスすることで、場所を問わずオフィスと同様の環境で業務を行えるシステムです。
VDI導入でネットワークに依存してしまうと、サーバーへの負荷が高くなるというデメリットがあります。しかし、情報漏洩リスクが低いため、セキュリティ対策を強化でき、災害時にも遠隔地から業務ができるようになることで、BCP対策も強化できます。
VDIはサーバーですべての処理を行うため、スペックの高いPCを社員一人ひとりに用意する必要がなく、コストの削減にもつながります。VDI製品やサービスを選ぶ際には、導入目的を明確にし、本記事で紹介したポイントを参考に自社に合ったサービスを選びましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ
あなたへのおすすめ記事

