購買管理の業務フローとは?購買管理の5原則・効率的な方法も解説

Check!
- 購買管理の5原則には、適正な取引先の選定や品質の確保などがある
- 購買管理業務は、複数会社から見積もりを出してもらってから購入先を選定する
- 購買管理業務を効率的に行うには、購買実績を把握しやすい購買管理システムがおすすめ
購買管理とは、企業にとって必要な商品を効率的に調達し、品質や納期などを確保するためのプロセスのことですが、適切な購買管理の遂行は難しいです。本記事では、購買管理業務の流れや、購買管理を行うに当たって重要な5原則、購買管理業務を効率的に行う方法を解説します。
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
購買管理とは

購買管理は、企業が必要な物品やサービスを計画し、調達し、適切な条件で提供する業務です。これには、供給業者の選定・価格交渉・契約締結などが含まれます。購買管理は在庫を最適化し、コストを削減することで企業の効率性と収益性を向上させます。
また、信頼性のある供給業者との協力関係の構築も重要で、リスク管理に役立てることが可能です。購買業務は質の高いものを、適切なタイミングで必要な量だけ調達する必要があり、マーケティングのスキルや経験が求められるため難しいとされています。

購買管理とは?業務フローやメリット、必要な内部統制についても解説
購買管理とは、企業が生産活動に必要な製品やサービスを適切に購入し管理することです。購買管理を行うことで、原価の低減による利益向上や社内の不正防止に繋がります。この記事では、購買管理の業務フローや必要な5原則、内部統制などについて解説します。
購買管理の5原則

購買管理を成功させるためには、考慮すべき重要な原則が存在します。ここでは、購買管理の5つの重要な原則について詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
購買管理の5原則
適正な取引先の選定
適正な取引先の選定は、信頼性・品質・価格・納期など、多くの要因を考慮して行われます。正しい取引先を選ぶことが製品やサービスの品質を確保し、コストの最適化につながります。
例えば、製品に必要な部品や素材を供給してくれる取引先を選ぶ際、その取引先の信頼性が重要です。長期間にわたる協力関係を築くために、信頼性が高く納期を厳守している供給業者を選別しましょう。
適正な品質の確保
品質の確保は、企業が取引先から入手する製品やサービスが高品質であるかを確かめる際に大事です。品質が低いと企業の評判が傷つき、競争に影響が出る可能性があります。
適正な品質を確保することで、製品やサービスが顧客の期待を満たし、顧客満足度の向上によってリピート顧客が増えます。さらに、高品質なものを提供し続ければ、保証やクレーム処理に関わるコストを抑えることが可能です。
対して、品質の低い製品やサービスには、大きな追加コストがかかることがあります。
適正な数量の決定・確保
不適切な数量の購入は、在庫の過剰な蓄積や不足につながり、コストが増加する恐れがあります。しかし、適正な数量の決定・確保により、企業が購入する製品やサービスの数量を正確に決定し、必要な分だけを確保できます。
企業は在庫コストを最小限に抑えつつ、キャッシュフローの最適化が可能です。また、必要な製品やサービスを適切なタイミングで入手できるため、生産効率と顧客満足度の向上につながります。
適正な納期の決定・確保
適正な納期の決定・確保は、企業が購入する製品やサービスの納期を正確に決定し、納期通りに確保することです。不適切な納期が決められて不備が生じると、生産計画やプロジェクトの遅延、顧客への迅速なサービス提供の妨げとなります。
仕入れや商品・サービスの完成を考慮し、納期を厳守することで企業は生産過程をスムーズに進行させ、顧客に対する信頼性を確保できます。
適正な価格で購入
企業が製品やサービスを調達する際には、公正かつ適正な価格での取引・購入が重要です。過度に高い価格で購入するとコストが上昇し、収益性が損なわれやすくなります。
反対に、安すぎる価格で購入すると品質やサービスが担保されず、企業の評判と競争力の低下につながります。そのため、適正な価格での取引・購入を続ければ、信頼できる取引先との長期的な関係を築くことも可能です。
購買管理の業務フロー

購買管理には、購買依頼書の申請から見積もりの依頼など、請求書の処理・支払いまでの主な業務フローが存在します。ここでは、購買管理の基本的な業務フローを解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
購買依頼書の申請
購買依頼書の申請は、調達における最初の工程です。特定の製品やサービスを購入する必要がある場合、まずは購買依頼書を記入して提出します。この書類には、購入希望のアイテムの詳細情報・必要な数量・納期・予算などが詳しく記載されています。
通常、購買依頼書は上司や購買担当者によって審査・承認されます。承認が得られると次の段階に進み、商品やサービスの調達が行われます。
見積もりの依頼
購買依頼書が承認されると、購買担当者は次の段階として、適切な取引先に見積もりの依頼を行います。これは、購入したい商品やサービスの詳細情報を伝える工程です。
購買担当者は、取引先に対して何を購入したいのか、どの程度の数量が必要なのか、そしていつ納品が必要なのかなどを明確に伝えます。
取引先はこの情報をもとに価格見積もりを提供し、どの程度の費用がかかるかを示して提供する商品やサービスの詳細を説明します。購買担当者は異なる取引先から提供される見積もりを比較し、最適な選択肢を選ぶことが可能です。
購入先の選定
見積もりが提出された後、購買担当者は異なる取引先の提案を評価し、最適な購入先を選びます。この段階では、価格・品質・納期・信頼性などが考慮されます。
特に、製品やサービスが必要なときに提供されないと、業務の遅延が生じる可能性があります。そのため、選定する際にはこれらの要因をバランスよく考慮しなければなりません。
例えば、価格が安くても品質が悪かったり、納期が遅れたりする場合は全体的な効率性に悪影響を及ぼす可能性があるため、最適な取引先を見つけることが重要です。
発注
選定された購入先に対して発注が行われます。発注書には商品やサービスの詳細が含まれ、価格や数量などが確定します。
例えば、オフィス用家具を購入する際、購入先に対して発注書が作成されます。この発注書には、家具の種類・仕様・数量・価格・納期などが詳細に記載されており、発注書を通じて家具の供給業者との正式な契約が成立します。
入荷・検収
発注した商品やサービスが正確に到着したら、品質検査を行います。注文内容が正確に受け取られたかどうかを確認し、品質に問題がないかをチェックします。注文内容と受け取った商品やサービスが一致し、品質に問題がないことを確認しましょう。
仮に商品やサービスに何か問題があった場合は、速やかに取引先に連絡し、問題の解決に努めることが大切です。品質検査は、誤った商品やサービスを受け取るリスクを軽減し、顧客への品質確保につながります。
請求書の処理・支払い
供給業者からの請求書を受け取ったら、契約条件と照らし合わせて正確性を確認します。注文内容や価格、支払い条件などが契約通りかどうかを確かめ、何か問題があれば供給業者との調整が必要です。
請求書を確認して問題がなければ承認し、支払い手続きを進めます。また、支払いに関連する文書(請求書、受領書、発注書など)は適切に記録・保管しておきましょう。
これらの文書を整理して保管しておくことで、将来の参照や監査に備えられ、組織内における透明性の向上と効率性の担保にも役立ちます。
購買管理業務フロー図の作成手順

購買管理業務を適切に行うには、自社独自の購買プロセスを業務フロー図として明確にする必要があります。ここでは、購買業務フロー図の作成手順を解説します。
関連部署と必要書類を洗い出す
購買業務フロー図の作成においてまず初めにすべきことは、購買管理業務に関係する部署と必要な書類を漏れなく洗い出すことです。フロー図を作成する際の基盤となるのは、関連部署と必要書類の2つです。
どの書類をどこの部署で作成し、提出場所なども明確にすることで、自社の購買管理業務の流れが可視化されます。仮に、漏れがある状態で作成されたフロー図は正しい管理プロセスが実行できなくなるため、漏れがないよう注意しましょう。
フロー図を作成する
関連部署と必要書類の洗い出しが完了したら、Excelなどを使用してフロー図を作成しましょう。その際、矢印などを活用した図式で作成するとプロセスが一目でわかり、理解しやすいフロー図に仕上がります。
対して、文字のみで作成されたフロー図は視認性が低く説明書のように見えてしまい、フロー図を作成しても正しいプロセスで購買管理が行われない可能性があります。フロー図を作成する際は、わかりやすさを意識しましょう。
購買管理業務における課題

購買管理業務にはさまざまな課題が存在します。ここでは、購買管理業務における主要な課題に焦点を当て、それらがどのように企業に影響を及ぼすかを解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
購買管理業務における課題
部門ごとの購買による過剰在庫の発生
部門ごとの購買による過剰在庫は、購買管理における大きな課題です。異なる部門が独自に購買を行い、同じ商品や材料を重複して購入した場合、部門間のコミュニケーション不足が一因として挙げられます。
過剰在庫は資本の無駄遣いを招き、経費を増やす原因となります。また、需要に対して供給が過剰になることで価格競争が発生し、廃棄物も増加します。
このような問題を解決するためには、部門間での協力とコミュニケーションの強化が非常に重要です。適切な情報共有と調整を行いながら、効率的な購買活動を実現しましょう。
発注先の未整理による割高での購買
発注先が整理されておらず、異なる供給業者から同じ商品を購入するとコストが増加します。特に、競争によって価格が高騰するとコストが増加しやすくなり、組織にとって無駄な出費となります。
また、割引や契約条件を把握できておらず、効果的に利用できないと本来よりも割高での購入が生じます。さらに、一括発注や長期契約の条件が適用されていない場合、組織はコスト削減の機会を失い、大きな損失となる点も課題です。
発注ミスの発生
購買管理業務では、人為的なミスやコミュニケーションの不足が発生すると、誤った数量や商品を発注し、さまざまな問題に発展します。不必要な在庫が発生した場合、企業はその在庫を処理するためにさまざまなコストをかけなければなりません。
また、誤った商品を受け取った場合、返品や交換が必要となり、手続きや再発注にかかる追加コストが発生します。そして、発注ミスが供給の遅延を引き起こす可能性もあり、商品が適切な納期に届かないと業務が滞り、企業の信頼性が低下することも考えられます。
購買管理業務を効率的に行う方法

購買管理業務にはさまざまな課題が存在しますが、これらの課題を解決するために、以下で購買管理業務をより効率的に行う方法に焦点を当てて紹介します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
Excel
Excelは低コストでの使用が可能であり、直感的な使い方ができるため、購買管理業務に幅広く利用されています。ただし、簡単なデータの整理やリスト作成には非常に適していますが、大規模なデータ処理や高度な分析には限界があります。
Excelのデータ入力は手動で行うため、入力ミスや計算を間違えるリスクが常に潜んでいます。また、リアルタイムのデータ更新や複数ユーザーによる同時アクセスには向いておらず、大規模なプロジェクトを含めた取引の管理には不便が生じやすいです。
特に、多くの取引先や商品情報を管理するほど、情報の整合性や正確性を保つことが難しくなるため、限定的な用途で使用するのがおすすめです。
アウトソーシング
アウトソーシングは、購買管理業務を外部の専門業者に委託する戦略です。外部プロバイダーは購買に関する最新の専門知識を持っており、企業はその知識を活用できます。
さらに、購買活動を外部に委託することで、企業は内部リソースを他の戦略的な活動に集中でき、コスト削減が可能です。外部プロバイダーはコストを最適化できるため、経済的なメリットもあります。
一方、アウトソーシングはセキュリティリスクが増加する可能性が高く、企業は外部プロバイダーとの情報の取り扱いに細心の注意を払わなければなりません。アウトソーシングの検討時には、潜在的なリスクとメリットをバランス良く評価することが大切です。
購買管理システム
購買管理システムは、組織内での購買業務をスムーズに進めるためのツールです。業務の自動化によって手作業を減らすことで、同じ作業を繰り返す必要がなくなり、ヒューマンエラーを削減できます。
また、購買管理システムはリアルタイムでデータを収集・分析できるため、正確な在庫情報の維持が可能です。その結果、需要と供給を調整しつつ、組織全体の業務効率化と管理体制の強化につながります。

購買管理システムは、企業が商品購買活動を行う際のプロセスをシステム上で行ったり、取引情報を管理したりするシステムです。この記事では、購買管理システムの主な機能やシステム導入によるメリット・デメリット、導入の際の比較ポイントなどを詳しく解説します。
購買管理業務を効率化するメリット

購買管理業務は企業のコスト管理や経営の効率性に関わるため、効率化によって大きな利益につながります。ここでは、購買管理業務を効率化するメリットについて解説します。
業務負担の軽減とスピーディーな購買管理が可能
購買管理業務における多くの手作業と確認作業を効率化すれば、作業者の業務負担を減らしてスピーディーな購買管理が可能になります。例えば、発注の流れを自動化したり、承認フローの電子化、仕入れ先とのデータ連携を図ったりすることで、業務効率が高まります。
さらに、購買管理システムや在庫管理システムの活用により、リアルタイムでの在庫管理状況の把握、適切なタイミングでの発注などが可能です。過剰在庫を抑えながら在庫不足や無駄な発注を防ぐことができ、緊急な対応にかかる負担の軽減も図れます。
交渉力の増加とコストの最適化につながる
購買コストの削減は、企業の利益に大きく関わります。特に、仕入れ先が固定されている場合は価格交渉がしづらく、現状のコストが適正かどうかの判断もしづらいです。
また、どの部署が発注したのかが判断できないと、不要なものを発注してコストが増加します。しかし、他部署との共同購入や購買ルールの明確化に加え、購買データの分析でコストの最適化を行うことで、交渉力の増加と仕入れ単価の購買コスト削減が可能です。
購買管理システムを選ぶ際のポイント

適切な購買管理システムを適切に選ぶためには、さまざまな要因を検討する必要があります。ここでは、購買管理システムを選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
購買管理システムを選ぶ際のポイント
導入目的を明確にする
導入目的の明確化は、購買管理システムを導入する上で非常に重要なポイントです。導入目的が明確でない場合、システムの選択基準が曖昧になり、システム導入後に期待通りの成果を得ることが難しくなるため注意しましょう。
導入目的に合致する購買管理システムを選ぶためには、どのような機能や特性が必要かを明確に設定します。例えば、コスト削減を目指す場合は、価格交渉支援や調達分析機能が必要です。そして、効率化を目指す場合は自動化やワークフロー管理が重要です。
誰でも使いやすい操作性か
購買管理システムは多くの従業員が利用するツールであり、使いやすさがポイントです。簡単に操作できるシステムは、作業の効率化やユーザーの満足度向上につながります。
操作性に優れたシステムは手間をかけずに必要な情報を素早く入手できるため、業務がスムーズに進行します。対して、複雑で理解しづらいシステムは作業に時間がかかり、誤った操作が発生する可能性が高まります。
生産性が低下するとユーザーの不満にもつながるため、使いやすい購買管理システムによってスムーズな業務遂行を図り、ユーザー満足度の向上を図ることが大切です。
既存システムと連携できるか
購買管理システムが既存システムと連携することで、データの一元管理が可能となり、データの一貫性と信頼性が向上します。さらに、リアルタイムな情報共有が可能になり、在庫状況の把握や需要と供給の適切な調整で予算管理も正確に行え、予算超過を防げます。
具体的な連携システムには、在庫管理・経理・生産計画・データ分析などが挙げられます。これらのシステムとの連携により、購買の流れが最適化されます。
サポート体制は充実しているか
購買管理システムのサポートが充実していると、システムの安定性を保つだけでなく、問題発生時のスピーディーな対応にもつながります。
サポートを利用する際に重要なポイントは、サポートの範囲・問い合わせ方法・対応時間の3つです。電話・メール・チャット・オンラインフォームなど、問い合わせ方法はさまざまなため、自社の希望の問い合わせ方法が可能なシステムがおすすめです。
また、他のユーザーの評判から、サポートの品質や対応速度を調査することも大切です。購買管理システムのトラブルや、運用時の問題発生時に迅速な対応を受けられるシステムを選びましょう。
まとめ
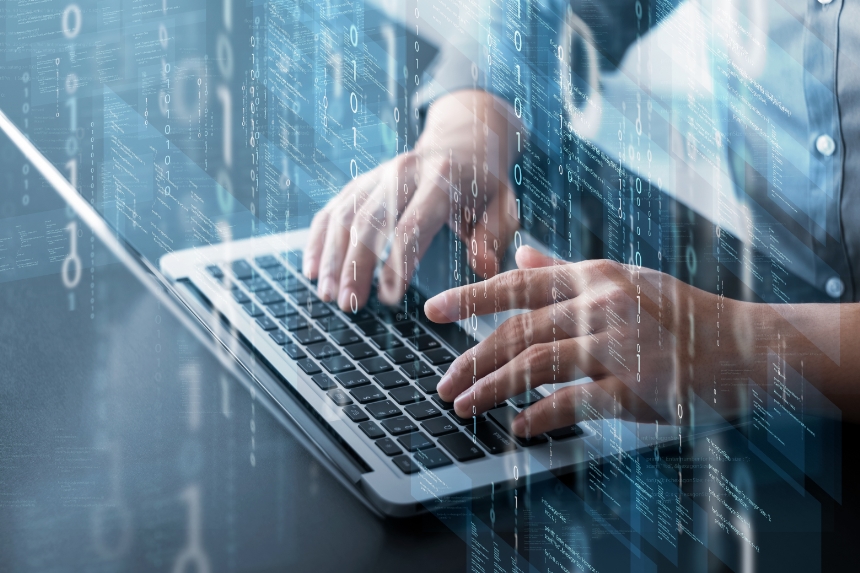
購買管理は、製品やサービスを買うための戦略を立てることです。具体的には、コストの計算や購入先の決定、契約管理、在庫の最適化などを行います。
購買管理システムを導入することで、これらの作業をスムーズにし、ミスを減らすのに役立ちます。導入する際には、目的や操作性、サポート体制などを確認し、自社のニーズに適合したシステムを選びましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

