電子契約の後文の書き方|文言例と必要性、書き方のポイントを解説
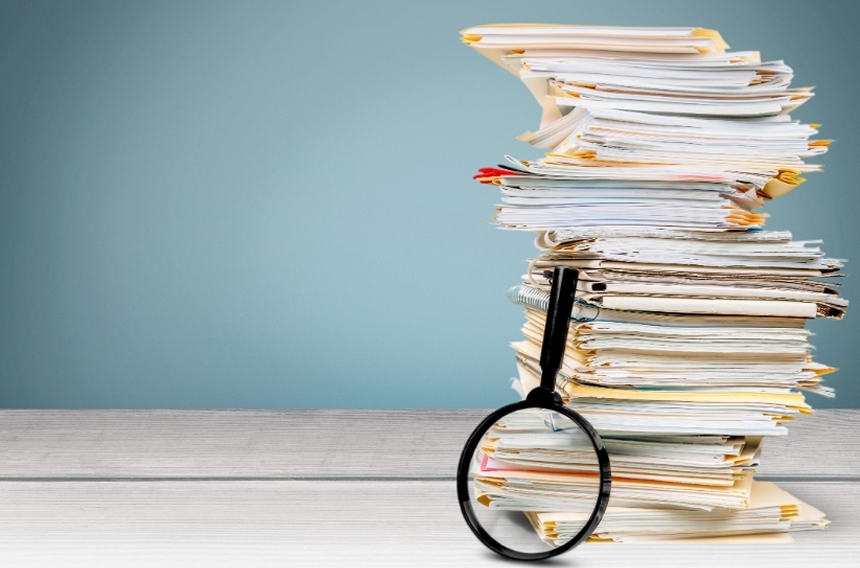
Check!
- 後文とは、契約に関する補足情報を記載する文章を指し、契約書の末尾に記載される
- 電子契約における後文では、「書面」の文言や作成枚数・保有枚数の記載は不要である
- 書面契約を電子契約に移行する際は、使用されている文言の変更に注意すること
後文とは、契約書の締結方法や保管方法について記す文章です。書面契約と電子契約では、後文に記載する内容が異なります。本記事では、後文の構成要素や、書面契約と電子契約での違い、書面契約を電子契約に移行する際の注意点などについて解説します。
おすすめ記事
契約書の「後文」とは

契約書の「後文」とは、契約書の末尾に記載される文のことを指し、読み方は「こうぶん」です。後文は契約成立の証拠として、当事者同士が合意し、契約を締結したことを文書化します。契約締結日や契約書の保管方法が明記され、契約関係の整合性を保ちます。
また、後文には契約の運用に関する基本的なルールや規則も含まれ、当事者同士が予期せぬトラブルの回避にも繋がります。後文の明確な記載は、契約の信頼性を高め、契約関係の運用の円滑化に期待できます。
電子契約と書面契約での後文の違い

電子契約と書面契約では後文の書き方に違いがあります。書面契約では、物理的な契約書に記載されるため、後文は紙上で明確に記載される必要があります。
一方、電子契約ではデジタル形式で契約が成立するため、後文もデジタルフォーマットに適した内容となるよう工夫する必要があります。以下に、電子契約と書面契約での後文を作成するポイントについて詳しく解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
電子契約と書面契約での後文の2つの違い
書面契約での後文に必要な構成要素
書面契約において後文は、重要な役割を果たします。契約締結日や当事者の同意、合意の証としての契約書の保管方法などが後文に記載されます。ここでは、書面契約の後文に必要な構成要素について解説します。
契約書作成の目的を記載する
契約書作成の目的を後文に記載することで、契約がなぜ締結される必要があるのかが明確に伝わります。たとえば、契約書においては、契約の内容や取引の背景を説明し、当事者間の合意に至る過程を示すことがあります。
これらを記載することで、自社と相手方で契約内容の認識のズレを防ぎ、不明瞭な点によるトラブルや将来の紛争防止に繋がります。また、後文に記載する目的によって、契約書の性質や範囲が明確になり、双方の合意が適切に反映されることになります。
契約書作成の目的を後文に記載することは、契約の透明性と法的な正当性を確保するために重要なポイントです。
契約書の作成通数を記載する
契約書の後文には、契約書を作成する通数を明記することが重要です。通常、契約書は当事者同士によって2通作成され、それぞれの当事者が1通ずつ保有します。これにより、契約の締結事実と内容を双方が証明する手段となります。
また、契約書の作成通数は法的な効力を保証する上でも重要であり、双方の同意に基づく契約の有効性を確保します。このように、契約書の作成通数を後文に記載することで、契約の成立とその効力を示す役割を果たします。
契約書の作成者・保有者を記載する
作成者とは、契約書を起草し作成した当事者を指し、保有者は契約書の原本を保管する当事者を指します。これらを記載することで、契約の当事者間での役割が明確になり、契約書の保管もしやすくなります。
また、契約書の作成者と保有者の記載は、契約の成立や効力を裏付ける要素として重要であり、紛争時にも契約の正当性や信頼性を証明しやすい利点があります。適切な作成者と保有者の指定は、契約の透明性と実効性を確保するためにも必要です。
契約締結の方法を記載する
書面契約の後文には、契約の締結方法も記載されます。具体的な締結方法を示すことで、契約の成立手続きを明確にする役割があります。締結方法は、契約書の交付と受領、署名と捺印、郵送や配達の方法などが含まれます。
これにより、契約当事者がどのような手順で締結したかを示すことができ、後々の紛争やトラブルの防止にも期待できます。特に、契約書の正式な提供と受領、署名と捺印の適切な手順の明確化は、契約の有効性を確保する上で重要なポイントです。
契約締結日を記載する
契約締結日は、当事者が契約を成立させた日を明確に示す重要なポイントです。契約締結日の明記により、その契約がいつから効力があるかを示し、後の法的な取り決めの際に有益となります。
特に、契約による権利と義務の発生や履行期限の判断において、契約締結日の明確な証拠は不可欠です。この情報を明確に記載することで、契約がいつ成立したかを双方が理解しやすくなり、契約の解釈や実行における諸問題の解決が円滑に行われます。
電子契約における後文のポイント
ここでは、電子契約における後文のポイントを解説します。電子契約は、書面と異なる部分がいくつかあります。電子契約におけるポイントを理解し、適切な表現で後文を記載しましょう。
作成枚数・保有枚数は不要
電子契約では、改ざんが難しい形でファイルを作成でき、そのまま複製・共有も可能です。そのため、同一のデータを自社と相手方双方でやり取りしやすく、紙のように「何通作るか」や「誰が何通保有するか」といった記載は不要になります。
また、通常の契約書と異なり、電子契約では作成したファイルの複製や保有に制約がなく、複数の当事者が同じ内容の電子ファイルを保管できます。これにより、契約の締結や保管の効率化を図りながら、法的な効力を保てます。
契約締結の方法が異なる
電子契約における契約締結方法は、書面契約と異なります。書面契約では通常「記名押印により」「サインの上」などが用いられますが、電子契約の後文では「電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する」などと表現されます。
また、電子契約では契約書を電子ファイルで作成し、電子署名をすることで、契約を締結します。電子署名には、誰がその契約に合意したかを証明する法的な効力があり、契約が正式に成立したことを示せます。
タイムスタンプを付与する場合
電子契約書では、タイムスタンプを付与することで契約締結日を確認できますが、その他の状況や文脈を考慮すると、契約締結日欄を省略することもあります。
しかし、契約の文脈や日付の重要性を考えると、電子契約書上に日付を記載することが望ましいです。これにより、契約が成立した日を明確に示し、紛争時の証拠としても有効となります。

おすすめの電子契約システム9選|選び方や導入手順を詳しく解説
電子契約システムとは、PDF形式の契約書にインターネット上で押印や署名をして契約締結できるシステムのことです。システムの導入をしたくても種類が多くてどれを選べば良いか分からない企業もあるでしょう。本記事では、おすすめの電子契約システムと選び方を解説しています。
電子契約における後文の例

ここでは、紙契約と電子契約における後文の例について解説します。まず、紙契約の後文の定型文例は以下の通りです。
【紙契約の後文の定型文例】
紙契約では、一般的に「本書」や「書面」といった文言を用います。また、契約者の人数に応じた枚数を作成するため、原本の存在証明として作成枚数に応じて後文に「◯通」と明記し、契約日の記載も必須になります。
以下は、紙契約の後文の一般的な例文です。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。
20××年〇〇月△日
甲:住所・会社名・氏名
乙:住所・会社名・氏名
【電子契約における後文の定型文例】
電子署名の契約書では、署名欄の代わりに電子署名を使用し、契約締結の過程や署名者の識別方法を明示します。具体的には、電磁的記録の作成と電子署名の施行、保管方法を指定し、当事者の同意を確認しましょう。
また、電子契約においては、電子契約サービスを用いて契約を締結するのが一般的です。しかし、自社と相手方で同じ電子契約サービスを利用している場合だけでなく、別のサービスを併用していたり、紙契約と併用して電子契約を行うなどさまざまなパターンがあります。
これらのパターンに応じて、適切な後文を用いることが求められるため、以下で紹介する例文を覚えておくと、スムーズに契約作業を進められるでしょう。
同じ電子契約サービスを利用する場合
自社と相手方など、契約を結ぶ当事者たち全てが同じ電子契約サービスを利用する場合、末尾に記載する後文も電子契約に対応した形式にしておくことが重要です。
以下は、同じ電子契約サービスを利用する場合に用いられる後文です。
本契約の成立を証するため、本契約の電磁的記録を作成し、甲乙各自が合意ののち電子署名を施し、それぞれがその電磁的記録を保管する。
20××年〇〇月△日
甲:住所・会社名・氏名・メールアドレス
乙:住所・会社名・氏名・メールアドレス
他の電子契約サービスと併用する場合
自社と相手方で異なる電子契約サービスを利用して電子契約を行う際は、どのサービスを使用して署名を行うのかを明示しましょう。
例えば、自社はAのサービスを利用しているが、相手方はBのサービスを利用している場合、両者が同一内容の契約書に合意し、それぞれが自社の利用するサービス上で電子署名を行うことで契約を締結します。
他の電子契約サービスと併用する場合、以下のような後文を用いるのが一般的です。
本契約の成立を証するため、本契約の電磁的記録を作成し、甲乙各自が合意ののちAおよびB上において電子署名を施し、それぞれがその電磁的記録を保管する。
20××年〇〇月△日
甲:住所・会社名・氏名・メールアドレス
乙:住所・会社名・氏名・メールアドレス
紙契約と電子契約を併用する場合
近年、電子契約を推進する企業は増えていますが、相手方によっては、電子契約ではなく紙での契約を希望する場合もあります。そのため、相手方の意向により一方は電子契約、もう一方は紙の契約書によって契約を締結するケースも少なくありません。
そのような場合は、契約の当事者それぞれが異なる形式で締結することに合意し、それぞれの契約形式と保管方法を明示しましょう。
紙契約と電子契約を併用する場合、以下のような後文を用います。
本契約の成立を証するため、本契約の書面および電磁的記録を作成し、甲乙各自が合意ののち記名押印および電子署名を施し、甲は書面を、乙は電磁的記録をそれぞれ保管する。
20××年〇〇月△日
甲:住所・会社名・氏名・メールアドレス
乙:住所・会社名・氏名・メールアドレス
紙の契約書を電子契約に移行する際に変更が必要な箇所

紙の契約書を電子契約に移行する際には、いくつかの変更が必要です。ここでは、移行する際に変更が必要な箇所について解説します。以下の変更点に留意し、スムーズに電子契約に移行しましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
紙の契約書を電子契約に移行する際に変更が必要な3つの箇所
「本書」「書面」の文言
従来の紙での契約では、書面があることを前提とする「本書」「書面」といった表現を用います。しかし、電子契約ではこの表現は適切ではないため、代わりに「電磁的措置」や「電磁的記録」など電子的な性質に即した用語に変更することが重要です。
また、契約締結時には電子データを「原本」とし、印刷した文書を「写し」と呼ぶことで、電子契約の特性を的確に反映できます。電子契約に適した文言に変更することで、法的な正確性と適合性を確保します。
作成通数・保有通数に関わる文言
書面契約書では契約書を複製した場合、後文に「本書を2通作成し」といった記載がある場合が多いです。しかし、電子契約に用いる電子ファイルは、基本的に改ざんが難しいため、作成通数、保有通数の記載は不要であることが一般的です。
電子契約では、何通作成した場合でも、その全てが原本と一致することになります。そのため、電子契約書の後文には作成通数・保有通数の記載が不要となります。
署名・押印に関する文言
書面契約で用いられる「記名」や「押印」といった表現は、電子契約において適切ではありません。電子契約では、契約の成立を証明する方法として、法的効力を持つ電子署名が使用されます。
電子署名は、契約当事者が内容に同意したことをデジタル形式で証明するもので、紙の契約における「記名押印」と同等の効力を持ちます。そのため、契約書に電子署名を使用することは、契約当事者間での合意と法的な信頼性を確保するために重要です。
電子契約導入におけるその他の注意点

電子契約導入に際して、文言修正だけでなくいくつかの注意もあります。ここでは、電子契約導入におけるその他の注意点について解説します。以下の注意点に考慮しながら、電子契約を導入し、契約管理の効率化を図りましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
電子契約導入におけるその他の注意点は3つ
社内の業務フローを見直す
電子契約を導入する際は、社内の業務フローを見直し、電子契約に最適化したフローの構築がおすすめです。電子契約は、締結の方法や保管方法など、書面による契約と異なる点も多いです。
例えば、紙への出力や決裁時の押印などの作業が不要になるため、文書の作成から署名、保存までを効率的に行えます。したがって、現在の業務フローにおいて省略できる作業があったり、さらに電子化を進められる業務も出てくるでしょう。
電子契約に合わせた業務フローは、正確な情報共有と納期遵守を促進し、業務の効率化やスピーディーな契約締結に繋がります。
法に対応する
電子契約導入時には、電子署名法、電子帳簿保存法、e-文書法などの関連法に考慮する必要があります。これらの法律は、電子契約の有効性や保存方法、取引記録の法的性格などを規定しています。業務フローの見直しなどの際は、これらの法律を考慮することが重要です。
業務フローの見直しにおいて、法に対応するためには法律の要件を理解し、電子契約の作成、署名、保存、証拠の取得などを適切に行うプロセスを構築する必要があります。
顧問弁護士などのアドバイスを得ながら、法的コンプライアンスを確保し、信頼性と法的効力を持つ電子契約システムを導入することが重要です。以下では、電子署名法、電子帳簿保存法、e-文書法の3つの法律について解説します。
電子署名法
電子署名法は、電子文書における電子署名の有効性や法的効力を規定する法律です。電子署名は書面署名と同等の法的効力を持ち、真正性と整合性を保証します。公的認証機関の信頼性ある署名提供や異なる署名方式の選択が認められ、国際基準にも合致します。
電子契約の効力保証や紛争解決手段も提供し、ビジネス取引の信頼性とセキュリティを確保します。個人や企業は電子署名を活用し、合意の確認や契約の実効性を高めることができ、安全性の高い電子取引環境の構築が可能です。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するルールを定めた法律です。対象は仕訳帳や決算書から領収書まで多岐にわたり、法定保存期間内であれば電子データでの保管が可能です。
電子帳簿保存法は、効率的な経理プロセスを支援し、紙媒体と同等の法的効力を持つ電子データを認めています。電子契約に関する書類も電子帳簿保存法に基づいて適切に保存する必要があります。
電子契約に関する書類も電子データで保存が求められ、これにより契約の信頼性が確保されます。電子契約導入時には、電子帳簿保存法の規定に基づいて適切なデータ管理体制を整えることが重要です。
e-文書法
e-文書法は、電子文書の作成・保存・送信などに関する法律です。主な特徴として、電子文書における契約の成立や通知の効力を認め、電子署名を法的な手段として導入しています。
これにより、電子文書が紙の文書と同等の法的効力が担保され、契約作業の効率化を図れます。法律に基づく電子署名は、証拠能力も認められ、行政手続や契約の遂行、紛争解決において信頼性を提供します。
また、電子文書の保存や提出についても要件を定め、長期間の信頼性を確保します。e-文書法は、デジタル社会における文書の取り扱いを法的に支援し、ビジネスのDX化をサポートする役割を果たしています。
相手方からの同意を得る
電子契約を導入する際は、相手方の同意を得ることが重要です。まず、電子契約の利点やセキュリティについて説明し、メリットを説明することで、相手方が電子契約の利便性や効率性を理解でき、同意が得やすくなります。
次に、信頼性を高めるために信頼できる電子契約サービスを選びましょう。業界で評判の良いサービスを選ぶことで、相手方に安心感を与えます。また、セキュリティ対策やデータ保護策についての説明も行い、情報漏洩のリスクに対する意識を持たせることが重要です。
また、同意を得るためには相手方とのコミュニケーションが欠かせません。電子契約導入の背景や目的を共有し、相手方の疑問や懸念点が出た際は真摯に応えることが重要です。
相手方の意向や状況も考慮し、電子契約の導入が相手方の業務に適しているかを確認し、適切な調整を行うことでスムーズな同意が得られます。
まとめ

後文は契約書の締結を確認し文書化する重要な部分です。電子契約における後文では、紙と異なる要点を考慮する必要があります。例えば、紙の契約では一般的だった作成枚数や保有枚数の記載は、電子契約では不要になります。
また、紙の契約から電子契約に移行する際は、文言の変更や業務フローの見直しが重要です。さらに、電子契約を進める際は、相手方の同意を得ることが必須です。メリットの説明や信頼性の高いサービスを選ぶことで、合意を得られやすくなります。
本記事で紹介した内容を参考に、電子契約において適切な後文を用いて、効率的かつ効果的な電子契約を実現しましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

