税務署の税務調査に対応するには|電子契約システムの有効性

Check!
- 税務調査とは、納税者が正しく税務申告ができているかを、税務署が確認すること
- 電子化された帳簿類は、電子帳簿保存法に則り正しく管理しなければいけいない
- 税務署の税調査に、適切に対応するには電子契約システムの導入が有効である
国税による税務調査のため、3〜5年の間に定期的に、税務署の調査官がやってきます。帳簿類を電子化している場合は、電子帳簿保存法に則り適切に税務調査に対応しなければいけません。本記事では、税務調査の概要から電子契約システムの有効性を解説します。
\おすすめの電子契約システムをご紹介/
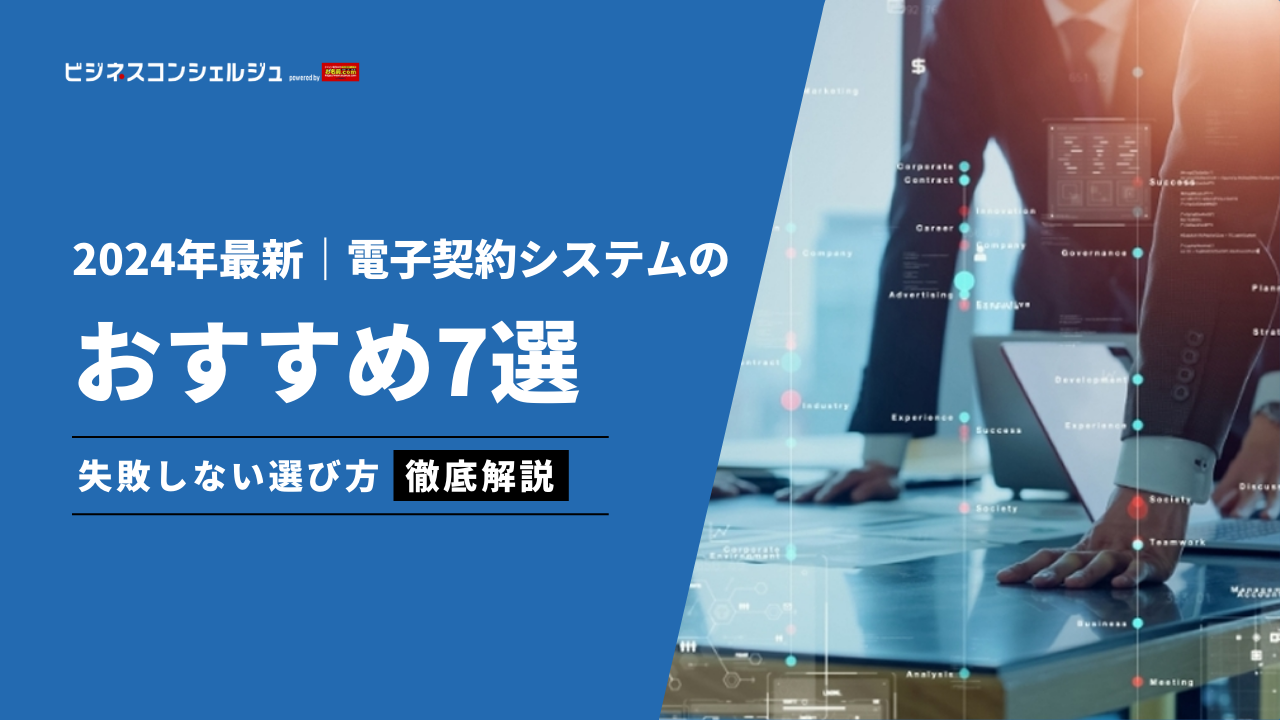
おすすめ電子契約システム7選(全46製品)を比較!【2024年最新/比較表付】
この記事を読めば、あなたの目的に合ったおすすめの電子契約サービスがわかる!電子契約ツールを法令への対応可否、機能性、サポートなどの観点から厳選しました。電子契約システムを導入したくても、種類が多すぎてわからない…そんなあなたにぴったりな電子契約システムを見つけましょう!
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
税務調査と電子帳簿保存法の概要

税務調査は、税務当局の調査員が、個人や法人の税務申告内容や税金支払いに関する情報を検証する手続きです。調査の目的は、税金の正確な評価と徴収を確保することで、税務調査では、申告書類や支払い記録などの提出が求められます。
一方、最近のテクノロジーの技術的な進展により、ネットワークやオンライン化が進み
電子契約システムなどの導入を多くの企業が検討しており、税務調査への対応にも有効な点が注目されています。
本記事では、税務調査や電子帳簿保存法の概要や改正の要件、電子契約システムにおける税務調査の内容、注意点などについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
税務調査と電子帳簿保存法の3つの概要
税務調査の概要
税務調査は、税務当局が個人や法人の税務申告に対して行う調査のことを指します。通常、3〜5年の間に調査官が訪れて行われます。主な目的は、正確な税金の申告と支払いが行われているかを確認し、税務法に適合しているかどうかを判定することです。
税務調査の種類として、税務署員が事業所などを訪問して調査を行う「外部調査」や、提出された書類やデータを基に行う「内部調査」があります。また、一定の要因に基づいて選ばれた申告者を対象に行う「選定調査」などがあります。
調査の結果、正確な申告が行われている場合は何も問題ありませんが、誤った申告や不正行為が判明した場合は、過去の課税期間に対する修正請求や追加の税金支払い、罰則が課せられる可能性があります。
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、企業や組織が電子的な方法で会計帳簿や取引記録を保存する際の基準や手続きを定めた法律です。目的としては、最近の情報技術の進歩に伴い、電子的な方法で会計情報を管理する需要が増加してきたために制定されました。
この法律の対象は、法人や個人などの事業主体となっており、会計帳簿や取引記録、給与台帳などの電子的な記録が含まれます。また、この法令に則り、電子帳簿の内容が改ざんされていないことを確保するためのセキュリティ措置や正確性が求められます。
電子帳簿の情報は法定記録保存期間に準じて保存する必要があり、閲覧可能な形式で保持する必要があります。この法律は、会計情報の電子化に伴う信頼性と法的効力を保証しており、適切な方法で保存や管理を行うためのガイドラインとなっています。
電子帳簿保存法改正の要件
電子帳簿保存法は、納税者の文書保存に係る負担軽減を図る観点から制定され、適宜改正も行われています。また、税務調査に対応するために法令の要件を満たす必要があります。ここでは、要件として「電子帳簿等保存」や「スキャナ保存」「電子取引」などについて解説します。
電子帳簿等保存
電子帳簿保存法や税務法などの法的要件に従って、電子化された会計帳簿や取引記録を保存することが法的な義務となっており、税務調査に備えるために、これらの法的要件を遵守することが重要です。
税務当局は、税務申告に関連する情報を基に、調査の対象となる企業や個人を選定します。調査の際には、保存された電子帳簿を提供することで、過去の取引や会計情報を確認し、申告内容と実際の取引が一致しているかどうかを判定します。
電子帳簿は、デジタル形式で保存されているため、必要な情報に対して迅速にアクセスし、確認することができます。これにより、税務調査の進行が円滑に行われることになり、税務当局への対応が効果的に行われることにもなります。
スキャナ保存
スキャナ保存は、紙の会計帳簿や取引記録の文書を電子的なデジタルデータに変換し、電子帳簿として保存する方法です。スキャナを使用して書類をスキャンし、デジタルファイルとしてPC内やクラウド上に保存することになります。
税務調査の際には、スキャナーで読み込まれて電子化された帳簿は、正確な取引記録や会計情報を提供するための重要な手段となります。税務当局はこれらの情報を確認し、申告された税金額が正確であるかどうかを検証します。
電子取引
電子取引は、eコマースや電子商取引とも呼ばれ、インターネットやネットワークを通じて商品やサービスを売買する取引のことです。ウェブサイトショップやオンラインショッピングなどを通じて注文や支払い、配送などのプロセスがオンライン上で行われます。
電子取引によって行われる売買や収入は、税務法上の課税対象となります。電子取引はデジタル形式で情報が記録されるため、税務当局はオンライン上の取引履歴や支払い記録を確認し、申告内容との整合性を確認することができます。
電子取引における税務調査は、デジタル時代において正確な税務申告と支払いが行われているかどうかを確認するために重要です。電子取引に関わる収入や支出を正確に申告し、税務法に適合することは、税務調査の円滑な進行と税金の適正徴収に貢献します。
税務調査に関わる電子帳簿保存法の内容

税務調査に関わる電子帳簿保存法の内容に関しては、「真実性の確保」や「可視性の確保」が重要になります。ここでは、それぞれの概要や税務調査との関連について解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
真実性の確保
電子帳簿保存法における「真実性の確保」は、電子帳簿が税務調査の際に正確な情報提供を行うために重要です。ここでは、その中の「訂正・削除履歴の保存」や「帳簿間の相互関連性」「関係書類の備付け」について解説します。
訂正・削除履歴の保存
電子帳簿の訂正や削除履歴の保存は、情報の正確性と透明性を確保するために重要な要素となります。税務当局が税務調査を行う際に、これらの訂正や削除履歴の保存は、正確な取引の記録を確認するために必要・不可欠となります。
税務調査の際には、税務当局は申告内容と実際の取引履歴が一致しているかどうかを確認します。電子帳簿の訂正や削除履歴を調査することで、過去の取引がどのように変更されたのかを確認し、申告内容との一致性を検証します。
このように電子帳簿の訂正や削除履歴を通じて、意図的な不正行為や虚偽の記録の改ざんがあったかどうかを検出することができます。不正が疑われる場合には、税務当局はさらに詳細な調査を行う可能性があります。
帳簿間の相互関連性
企業や組織の運営においては、会計帳簿や購買帳簿、売上帳簿、給与台帳などさまざまな帳簿が使用されます。これらは異なる情報を記録し、相互に関連性があります。例えば、売上帳簿と仕入帳簿は、売買取引の情報を記録し、財務諸表や税務申告に関連しています。
税務調査の際には、異なる帳簿間で記録された情報が一貫性を持っているかどうかが確認されます。例えば、売上帳簿に記録された取引が購買帳簿に反映されているかが調査され、取引の正確性が検証されます。
企業や組織は、帳簿を法的要件に基づいて適切に管理し、帳簿間の一貫性を保つ義務があります。税務調査の際には、これらの法的要件の遵守も確認されます。帳簿間の一致性を保ち、正確な情報提供により税務調査のスムーズな進行と公正な税金徴収が行われます。
関係書類の備付け
税務調査が行われる際には、企業や個人事業主などは関係書類の備付けとして、関連する書類や情報を提供することを指します。これにより、税務当局が正確な情報を収集し、税務申告の正確性や法的遵守を確認することが可能となります。
関係する書類としては、会社や組織の取引履歴や経費、収入などの会計情報を記録している会計帳簿があります。また、取引記録として、売上や仕入れ、支払い、収入などの取引に関する記録としては請求書、領収書、契約書などが含まれます。
そのほかの関係書類として給与台帳や資産台帳、納税申告書、契約書などがあります。これらの関係書類の提供により、税務調査の際に、法人の収支や取引履歴を詳細に確認することができ、税務法の遵守が確認され、正当な税金申告が検証されます。
可視性の確保
税務調査の際には、電子帳簿などの可視性を確保する必要があります。ここでは、その中の「検索機能の確保」や「見読可能性の確保」などについて解説します。
検索機能の確保
税務調査において、電子帳簿の検索機能の確保は重要で、的確な検索が行われることにより、税務当局は効率的に必要な情報を取得し、調査を迅速に行うことができます。一般的に電子帳簿は膨大な情報を含んでおり、手動で必要な情報を探し出すのは難しくなります。
検索機能により、特定の条件やキーワードを指定して情報を取得することができ、必要な情報を迅速に特定できます。例えば、特定の期間や取引内容などを指定して情報を検索することにより、目的の情報を短時間で探し出し確認することができます。
検索機能を利用することで、税務調査における必要な情報を正確に取得し、申告内容との整合性を検証することができます。また、情報収集が迅速に行えることにより、調査の効率が向上し、調査の労力と時間を節約できます。
見読可能性の確保
税務調査において、電子帳簿の見やすさと読みやすさを確保することは重要です。電子帳簿はデジタル形式で情報が記録されているため、優れた情報の整理と表示方法により、税務当局が必要な情報を容易に読むことができ、調査を効果的に行うことができます。
見やすく読みやすい電子帳簿の情報は、税務調査の際に、情報の誤解や誤読を防ぎ必要な情報を迅速に特定し、取引や情報の正当性を裏付けるクリアな証拠となります。また、税務当局と企業との間のより良いコミュニケーションを促進します。
電子帳簿の見やすさや読みやすさを確保することは、税務調査の効率性と正確性を向上させるために重要です。適切なフォーマットやフォントなどの活用を通して、電子帳簿の情報の整理と理解をサポートし、税務調査の進行をスムーズにします。
税務調査に関わるe-文書法の内容
e-文書法とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つの法律を指します。これは、国税関係書類など書面での保管が義務付けられていた書類において、電子データでの保存も認められた法律です。
ただし、電子データで保存するには以下の4つの要件があります。
- 見読性:パソコンやプリンタを用いて明瞭な状態で即座に表示・出力可能であること
- 完全性:保存期間中に電子データが滅失や毀損しないように措置が取られていること
- 機密性:不正アクセスの抑止措置が取られていること
- 検索性:必要な情報がすぐに引き出せる体制であること
参考:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律|e-Gov法令検索
電子契約システム導入後の税務調査の内容

電子契約システム導入後における、税務調査の内容としては、電子化された書類や帳簿データが調査されることになります。ここでは、その概要や利点などについて解説します。
書類や帳簿データを調査される
電子契約システムにより、取引関連の帳簿などがデジタルデータとして管理されるため、必要な情報を迅速に特定できます。そのため、税務調査の際には、必要とする取引情報や契約内容が、検索やフィルタリングを行うことで簡単にアクセス可能となります。
また、電子契約システムの利用において、取引が成立時に自動的に契約情報や取引内容が記録されるので、エラーが減り記録の精度が向上します。そのため、紙の領収書の記入や印刷の手間などが不要となり、経理担当者の負担を低減することができます。
電子契約システムの導入により、契約書などの帳簿がデジタルな情報として自動化され管理されます。その結果、税務調査時には、経理担当者は正確な情報が提供できるようになり、業務の効率化や調査への協力が可能となります。
電子契約システムで税務調査に対応する際の注意点

電子契約システム導入後に、税務調査に対応する際にはいくつかの注意点があります。ここでは、「電子化しても紙の原本が必要な場合がある」点や「電子契約システム導入前の証憑類」などについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
電子契約システムで税務調査に対応する際の2つの注意点
電子化しても紙の原本が必要な場合がある
帳簿を電子化する場合には、タイムスタンプの付与が義務付けられています。これは特定の日時にデータが作成されたことを証明する重要な要素です。タイムスタンプが付与されていない電子帳簿は、データの作成時期や変更履歴を特定し、確認することが難しくなります。
税務調査などの時点では、タイムスタンプのない帳簿のデジタルデータは信頼性を欠き、証拠として十分な力を持たない可能性があります。そのため原本の提示が必要とされる場合があります。
また、電子帳簿保存法などの規定に準拠していない場合、保存データの法的な有効性が認められないことがあります。例えば、法令ではデータの整合性やバックアップなどの要件があり、これを満たしていないと、データの信頼性が失われ、原本の提示が求められます。
電子契約システム導入前の証憑類
電子契約システムの導入前や書類を電子化する前の段階では、従来通り紙の証憑(しょうひょう)類が原本となります。そのため、税務調査の際には、電子化された契約書などのデジタルデータのほかに、紙の証憑類の準備も必要となります。
電子帳簿保存法は、特定の取引記録や書類を一定期間保存するための法律です。この法律に基づき、電子帳簿は一定の要件を満たして保存される必要があります。税務調査の際には、法令に準拠したデジタルデータや紙の証憑類の提示が求められることがあります。
電子契約システムを導入していると税務調査に適切に対応できる

電子契約システムを導入する際に、電子契約法や電子帳簿保存法などの関連する法的な要件に準拠してデジタルデータの登録や運用を行うことで、法的な基準を満たすことができます。これにより、税務調査時にも法的な正当性を示すことが可能となります。
電子契約システムに蓄積されたデジタルデータは、必要な情報を容易に検索できるため、税務調査の際にも情報の提供がスムーズに行えます。また、システムによりタイムスタンプが付与されたデータは作成時期や変更履歴を証明でき、データの信頼性を高めます。
電子契約システムの導入により法令の要件を満たすことで、データの正確性や信頼性、証拠としての有用性などを確保することができ、税務調査時に確実な情報提供などに適切に対応でき、法的なリスクも軽減されます。

電子契約システムとは、企業などが契約時に交わす署名や押印等の書類でのやり取りを電子上で行うことができるシステムです。この記事では、電子契約システムの仕組みや、メリット・デメリット、選び方や導入する際の注意点などを解説します。
まとめ

電子契約システムは、契約や取引をデジタルで管理し、法的要件を満たすことで税務調査などに対応できる重要なツールとなります。また、システム導入により、タイムスタンプやデータ整合性の確保、デジタルデータの容易な提供などが実現されます。
この機能により、税務調査時に信頼性のあるデータを証拠として迅速に提供できます。また、正確な情報提供と効率的な調査対応により、税務署の要求などに適切に対応し、法的リスクを軽減することができます。
今後、電子契約システムにおける電子契約と税務調査など関連を検討する際には、求められる要件や注意点などを考慮し、的確な対応を目指してください。
この記事に興味を持った方におすすめ

