コールトラッキングシステムとは?仕組みや選び方を詳しく解説

Check!
- コールトラッキングシステムは、オフライン広告の効果測定を可能にするシステム
- 費用対効果の検証だけでなく、見込み顧客の流出防止や顧客の一次情報取得にも役立つ
- 外部ツールとの連携可否や必要機能の有無など、導入前に詳細を確認することが重要
コールトラッキングシステムは、電話数や入電に至った経路などを可視化して計測するためのシステムです。この記事では、コールトラッキングシステムの仕組みや導入のメリット、選ぶ際の比較ポイントや利用時の注意点などを詳しく解説していきます。
おすすめ記事
目次
開く
閉じる
開く
閉じる
コールトラッキングとは

コールトラッキングとは、電話効果測定を意味し、電話での問い合わせ履歴を元に顧客情報の管理・分析の可視化を図るシステムを指します。取得できるデータは、入電時間・通話経路・流入経路・通話録音・発信者の電話番号・広告媒体の電話数などです。
SNSなどのアクセス解析のように、新聞やチラシ・雑誌などオフライン広告からの流入経路がわかり、広告媒体の効果測定が可能です。スマートフォンで電話番号をタップした回数をトラッキング対象として計測する「タップ計測」よりも精度が高くなっています。
また、通話情報や架電情報を活用して見込み顧客の流出を防止したり、一次情報の取得ができたりするのもメリットです。さらに、システム導入の際の費用も比較的安く抑えられ、導入までの日数も短いため、簡単にシステムの利用を開始できます。
コールトラッキングの仕組み

コールトラッキングは、電話番号を広告媒体やメディアに掲載し、利用者からの電話をコールセンターへ転送します。広告媒体ごとに異なる電話番号を掲載することで、どの広告から入電に至ったのかを計測するという仕組みです。
また、どの広告からの入電なのかだけでなく、入電のタイミングや通話時間などを蓄積するため、どの広告が最も効果があったのかなどを把握できます。
コールトラッキングシステムの機能
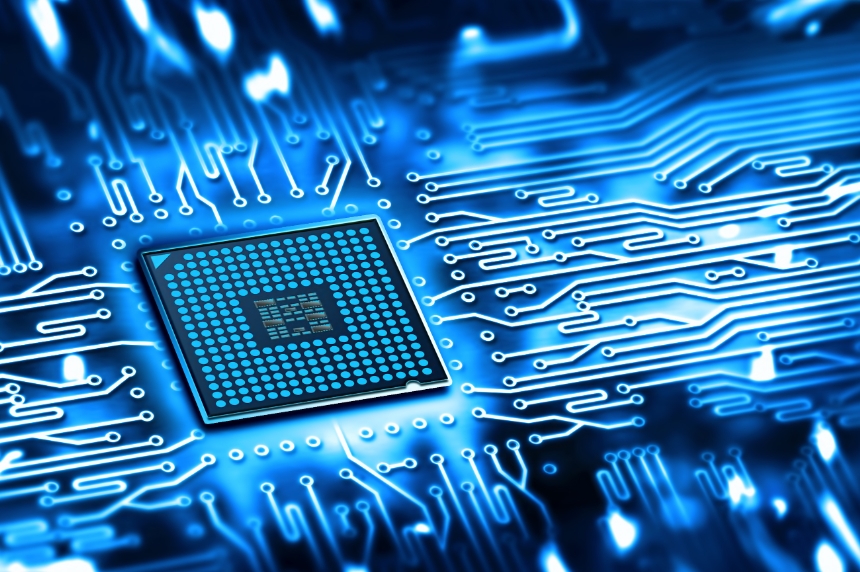
コールトラッキングシステムには、主に5つの機能があります。システムごとに搭載している機能は異なりますが、以下の5つの機能は、多くのコールトラッキングシステムが標準機能、もしくは追加オプションとして備えています。
| レポート・分析機能 | 経由した広告媒体や受電日時などを記録し、分析する |
| IVR機能 | 入電に自動で対応する(自動音声応答) |
| 録音機能 | 通話の内容を録音する |
| メール通知機能 | 入電が合った際に事前に登録したメールアドレス宛に通知を送る |
| 発信者番号の表示機能 | 入電時に発信者の電話番号を表示する |
コールトラッキングシステム導入のメリット

コールトラッキングシステムの導入により、どの広告媒体を介しての問い合わせなのかが簡単に測定できます。ネットでの問い合わせをトラッキングするだけでは、広告効果が正確に把握できません。
電話による問い合わせのトラッキングも併用すれば、より正確な広告効果がわかります。ここでは、コールトラッキングツールを導入するメリットについて、主なものを6つ紹介します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
コールトラッキングシステムの導入メリット
流入経路を確認できる
前述したように、コールトラッキングシステムはそれぞれの媒体・発信者別電話番号の顧客の流入経路を確認できます。広告ごとの効果を可視化することも可能なため、オンラインとオフライン両方の広告の改善につながります。
入電数だけでなく通話時間や内容なども記録するため、入電数は少ないが購買意欲の高い見込み顧客が多いなど、広告媒体ごとの特徴も明確になります。
費用対効果を検証できる
通常、商品やサービスの知名度アップや宣伝のために広告を出す場合は、オフライン広告を含む複数媒体を使用します。コールトラッキングツールを活用すれば、複数の広告媒体の各効果を具体的な数値で測定可能です。
また、得られたデータの分析により、費用対効果の高い広告媒体が明確になります。費用対効果の低い広告の停止や改善といった対策が取れ、無駄なコストの発生を防げます。
見込み顧客の流出を防止できる
電話で問い合わせをする顧客は、商品やサービスに高い関心がある見込み顧客であると予測できます。しかし、営業時間外やスタッフの不足などで電話対応ができなかった場合、そういった見込み顧客を逃がしてしまうかもしれません。
コールトラッキングシステムを導入することにより、電話番号の記録や、対応ができる電話への転送などが可能です。そのため、SMSやメールでフォローするなどの手段を使って、見込み顧客の流出を防ぐこともできます。
自動音声案内サービス(IVR機能)により業務の効率化ができる
コールトラッキングシステムには、IVR機能やガイダンス再生機能が搭載されているサービスが多いです。これらの機能は顧客の電話に合成音声や録音音声で対応し、管理担当者へ電話を転送したり、顧客に必要な操作をしてもらったりできます。
従業員がすべての電話に対応しなくても済むため、顧客対応の効率化が見込めるのがメリットです。また、顧客としても効率よく目的の部署へ電話を転送してもらえるため、メリットは大きいと言えます。
応対品質の向上を実現できる
コールトラッキングシステムの種類によっては、通話内容の録音機能や音声をテキスト化する機能が搭載されています。録音データや通話内容のテキストを確認することで、電話対応時の課題を把握し、対応品質の向上に活用できます。
例えば、架電数や通話数が多いにもかかわらず、サービスの購入などに結びつかない場合に、今までの通話履歴を見直し、営業台本を見直して品質を向上するといった対応がとれます。
顧客の一次情報を取得できる
コールトラッキングシステムの通話録音機能によって、顧客のリアルな声を取得できるのも大きなメリットです。
数字などの管理上のデータはもちろん、ユーザーから直接収集された信頼度の高い一次情報を生かせば、自社のマーケティングにおいてより具体的な対策が可能で、同業他社との優位性を確保しやすくなります。
数字上のデータでは読み取れないユーザーの深層心理を知りたい、さらに質の高いマーケティング施策を講じたいといった場合にも、コールトラッキングシステムはおすすめです。
コールトラッキングシステムの種類

ここからは、コールトラッキングシステムの種類とそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。自社のシステム状況に合うコールトラッキングのシステムを選択するために理解しておきましょう。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
コールトラッキングシステムの種類
電話番号ごとの入電情報のみ扱うシステム
広告媒体ごとに電話番号を割り当て、その番号ごとの入電に関するデータを扱うシステムです。例えば、複数の広告媒体を使用している場合に、どの媒体からの問い合わせ件数が多いのかを把握できます。
割り当てた電話番号ごとに件数や内容を収集するシンプルな機能のため、費用を抑えられる点がメリットです。コストを抑えて、電話の問い合わせの可視化に取り組みたい場合に向いています。
一方で、電話番号と広告媒体を関連付けてトラッキングするため、管理に手間を要するのがデメリットです。コスト面でのメリットと管理するための負担を比較し、どちらを重視するかを考慮したうえで、どのシステムがベストかを判断する必要があります。
サイト上の電話番号をセッションごとに切り替えるシステム
顧客がWebサイトを見て電話で問い合わせをしてきた際に、セッション単位でサイト上の電話番号を切り替えてトラッキングするシステムです。電話番号が確認できればどこ経由のセッションなのか把握できるため、コール単位のトラッキングに最適です。
コールのセッション単位でのトラッキングのため、Webサイトを変更・複製をせずに計測できます。Webサイトの管理負担を軽減でき、オンラインの広告効果と併せてオフラインの広告効果を測定したい場合に便利です。
しかし一方で、セッション数単位で電話番号が切り替わるため、大量の電話番号が必要となる可能性があるのがデメリットです。本来、電話番号は際限なく準備できるものではありません。特にフリーダイヤル(0120)の電話番号はその数が限定されています。
サイト上の電話番号を設定したルールで切り替えるシステム
一定のルールを設定し、Webサイト上の電話番号を切り替えてコールトラッキングを行うシステムです。大規模なWebサイトでも少ない電話番号でコールトラッキングに対応できるのがメリットです。
コールトラッキングツールのシステム上で個別にルールを設定するので、ツール本体に比較的高い機能が必要です。そのため、設定するルールによっては費用が高くなる場合があるのがデメリットです。
コールトラッキングシステムを選ぶ際の比較ポイント

コールトラッキングシステムの機能や種類ごとのメリット・デメリットなど、基本事項を解説しました。ここからは、コールトラッキングを選ぶ際にチェックしておくべき重要な比較ポイントについて解説します。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
コールトラッキングシステムを選ぶ際のポイント
費用は効果に見合ったものか
システム導入時には、費用対効果がどのくらい見込めるのかを把握することが重要です。コールトラッキングシステムは、導入後も長期的な計測・分析が必要になります。初期費用・ランニングコストを考慮し、長期的に利用できるか検討しましょう。
ツール利用料のほかにも、ツールの利用によってどの程度の工数削減できるかも含めて考えると、費用対効果が明確に把握できます。
自社業界・ニーズに合った電話番号を発行できるか
コールトラッキングシステムを選ぶ際は、自社業界・ニーズに合った電話番号を発行できるかを確認しましょう。電話番号には、0120・0800・050・0078などから始まる複数の種類があり、それぞれ特徴が異なります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 0120 | 通話料無料のフリーダイヤル 着信側が料金を負担する 認知度が高く顧客に安心感を与える |
| 0800 | 通話料無料 着信側が料金を負担する11桁で構成され、10桁の0120よりも桁数が多くなる |
| 050 | インターネット回線を利用したIP電話 導入コストが安い 発信側が料金を負担する |
| 0078 | 通話料無料 着信側が料金を負担する |
0120は古くから使われているフリーダイヤルのため、多くの顧客が安心して利用できる、といった特徴があります。また、050は飲食店や美容室などのポータルサイト上でよく使われている番号です。
自社の業種や顧客層も考慮しながら、利用したい電話番号に対応できるシステムを選びましょう。
外部ツールとの連携は可能か
ほかの分析ツールと連携できるコールトラッキングシステムであれば、分析精度をさらに高められます。コールトラッキングシステムを新しく導入する際も、自社で導入中の分析ツールとの連携可否をチェックしましょう。
外部の分析ツールもコールトラッキングシステムも、その導入目的は効果の高い広告の分析です。コールトラッキングで得たデータを外部の分析ツールにインポートできれば、分析結果の信頼度が向上します。
また、ツールが連携できればそれぞれを集計して分析する手間が省けます。効率良く分析作業を推進し、データを活用したマーケティング戦略に注力するためにも、他ツールとの連携性は重要です。
自社に必要な機能が備わっているか
コールトラッキングシステムには主に5つの機能(レポート/分析機能・IVR機能・録音機能・メール通知機能・発信者番号の表示機能)が備わっています。ツールによって搭載機能に差があるため、自社に必要な機能があるかどうかの確認が必要です。
無料トライアルがあるか
コールトラッキングシステムには、無料トライアルが提供されている製品も多数あります。自社のニーズに合った機能が搭載されているか、担当者が使いやすいかどうかを実際に操作して確認してみましょう。
また、機能面や操作性を確認するだけでなく、導入後の運用フローをイメージしておくことも重要です。複数のシステムを比較することで、より自社に最適な製品を選定できます。
サポートが充実しているか
コールトラッキングシステムは海外のサービスも多いため、日本での使用ではサポートが十分に受けられない可能性があります。
特にサポート窓口が24時間体制でない場合、時差により日本時間の夜中でないと問い合わせができないことも考えられます。万が一のトラブルなどに迅速に対応できるか確認しましょう。
コールトラッキングシステムを利用する際の注意点

コールトラッキングシステムを効率良く活用すれば、顧客の動向なども詳細に把握できるうえに、今後のマーケティング対策の検討も可能です。しかし、導入に関していくつかの注意点があるため、事前に確認しておく必要があります。
\気になる項目をクリックで詳細へジャンプ/
コールトラッキングシステムを利用する際の注意点
計測できる電話番号への折り返しを依頼する
原則としてコールトラッキングができる電話番号は限定されています。もし、顧客が電話で問い合わせをして、かけ直しの希望があった場合、コールトラッキングができない電話番号を伝えてしまうと計測ができません。
顧客から折り返し電話をもらう約束をするときは、コールトラッキングができる電話番号を伝えましょう。伝える電話番号については、電話対応をするスタッフ全員が共有しておくのが大切です。
バナー画像などに電話番号を掲載しない
コールトラッキングシステムを導入せず、各媒体の電話番号も全部同じ場合はホームページのバナーなどの画像に電話番号を記載しても問題はありません。
しかし、媒体によって違う電話番号を登録していれば、顧客が電話しても繋がらなかったといった混乱が生じてしまいます。そういった混乱を避けるためにも、バナーなどの画像には電話番号を掲載しないのがおすすめです。
まとめ

今回はコールトラッキングシステムについて解説しました。コールトラッキングシステムを導入すれば、電話内容をデータとして残し、各施策の効果をより正確に把握することが可能です。
また、自動ガイダンスによる業務の効率アップも期待できるため、コール担当者の不足で悩んでいる場合にもおすすめです。導入時は、選ぶ際の比較ポイント・利用時の注意点を確認し、自社に合ったシステムを選びましょう。
この記事に興味を持った方におすすめ

